 近年、「推し活」という文化現象が日本社会に大きなインパクトを与えています。アイドル、アニメキャラクター、スポーツ選手など、自分が応援したい対象を「推し」と呼び、その活動を支援する文化は、2021年には新語・流行語大賞にもノミネートされ、市場規模は8,000億円に迫っています。
近年、「推し活」という文化現象が日本社会に大きなインパクトを与えています。アイドル、アニメキャラクター、スポーツ選手など、自分が応援したい対象を「推し」と呼び、その活動を支援する文化は、2021年には新語・流行語大賞にもノミネートされ、市場規模は8,000億円に迫っています。
この巨大なエネルギーを持つ現代文化が、今、福祉の現場で革新的な変化を生み出しているのです。「推し活×福祉」は、単なる一時的なトレンドではなく、障害者支援のあり方を根本から見直し、新たな可能性を切り拓く社会変革の潮流として注目を集めています。
なぜ今「推し活」が福祉の現場で注目されるのか
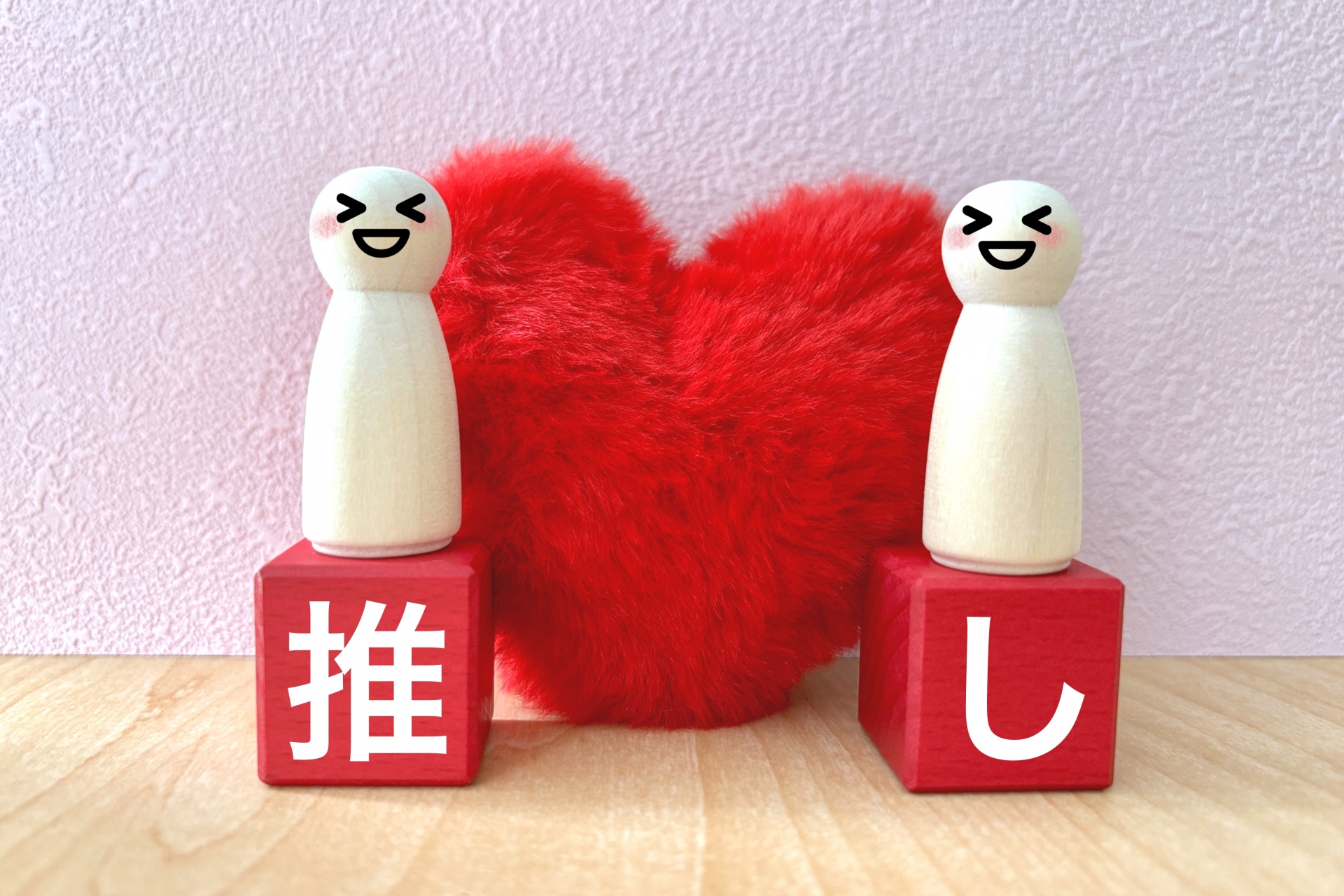 「推し活」は、福祉の課題に対する強力な解決策となる可能性を秘めています。なぜなら、推し活には人の心を動かし、人と人をつなげる力があるからです。
「推し活」は、福祉の課題に対する強力な解決策となる可能性を秘めています。なぜなら、推し活には人の心を動かし、人と人をつなげる力があるからです。
学術的な研究においても、推し活が幸福度や生きがいを高め、人生にポジティブな影響を与えることが示されています。「推し」という対象に夢中になることで、日常に彩りが生まれ、前向きな気持ちが育まれます。毎日の生活に張りが出て、明日への期待感が生まれる事例は多いです。
重要なのは、同じ「推し」を応援するファン同士のコミュニティが自然に形成される点です。共通の話題や目標を持つことで、初対面でも会話が弾み、一体感や所属感を味わえます。かつて内向的なイメージがあった「オタク」文化が、よりオープンで社会的な活動を伴う「推し活」へと進化して、誰もが参加しやすい文化となったことも大きな要因です。
社会的に孤立で寂しい思いをしている障害者や高齢者にとって、推し活コミュニティは家庭や職場以外の「サードプレイス」として機能し、生きる上での重要な支えとなり得ます。そこでは、障害の有無に関わらず「同じものを好きな仲間」として対等な関係性が築かれやすいのです。
【事例で見る】「推し活×福祉」の具体的なプロジェクト

「推し活×福祉」は、抽象的な理念ではなく、すでに具体的なプロジェクトとして各地で成果を上げています。
事例①【創る支援】:好きを仕事に。就労継続支援B型事業所「にじげんマルシェ」の挑戦
「創る支援」の先進事例として注目されるのが、株式会社エンピュアが運営する就労継続支援B型事業所「にじげん池袋」から生まれた店舗型ショップ「にじげんマルシェ」です。このプロジェクトの大きな目的は、利用者の「好き」という情熱を、専門的な「仕事」へと昇華させることです。
「にじげん」では、イラストや動画編集といったクリエイティブスキルに特化した「学習型就労支援」を提供しています。アニメや創作活動が好きな利用者たちが、業務用刺繍ミシンなどの本格的な機材を使用し、推し活に特化したオリジナルグッズを制作・販売しています。
重要なのは、これらの商品が推し活好きの現役デザイナーによって監修され、利用者の「こんなグッズが欲しい」というアイデアが実際の商品に反映される点です。利用者からは「自分が作ったものがお客様の手に渡り、ほめてもらえて自信がついた」「職員が優しく教えてくれるので『できない』が『できる』に変わった」といった声が寄せられています。
単なる作業ではなく、自らの情熱が注がれた創作活動を通じて、スキルアップはもちろん、他者から評価される喜びや社会とのつながりを実感できるところが好評です。
引きこもりがちだった人が毎日通えるようになるなど、メンタルヘルスの改善や生活リズムの安定にも大きく貢献しています。このモデルは、利用者の「好き」を原動力にしてやりがいと経済的対価を生み出す、新しい就労支援の形を示しています。
参考:【日本初 就労支援×店舗型”推し活”ショップ】業務用刺繍ミシンで障がい者の新たな働き方を創出 刺繍と推し活の専門ショップが池袋に新規オープン
この投稿をInstagramで見る
事例②【支える支援】:サポーターになる喜びが生きる力に。「Be supporters!」プロジェクト
「支える支援」の代表格が、サントリーウエルネス株式会社とJリーグが連携して進める「Be supporters!(ビーサポーターズ)」です。このプロジェクトは、高齢者施設の利用者が地元のJリーグクラブのサポーターとなり、選手を「支える」側に回るという画期的な取り組みです。
参加者は、応援する「推し」の選手を決め、応援グッズを作り、仲間とともに試合を観戦します。リハビリを嫌がっていた人が「立って応援したい」と自発的に体を動かし始め、食が細かった人が「サポ飯」作りをきっかけに食欲を取り戻した例も多いです。
他者と交流しなかった人が、推しの魅力を語るために笑顔で会話するようになり、外国人選手と話したい一心で外国語の勉強を始める人まで現れました。
特に印象的なのは、認知症を患う83歳の女性が、移籍した推しの選手に会うために神戸から鹿児島まで約850kmの「遠征」を実現させたという事例です。これは、推し活が持つ強力なモチベーションの力を如実に示しています。
これらの現象は、サントリー、京都大学、大阪公立大学の共同研究によって科学的にも裏付けられています。「推し活」への熱中度と「生きがい意識」が連動して変化することが確認されました。人とのつながりと、自分の希望をかなえたいという気持ちの両方が強くなることが分かったのです。
このプロジェクトは、応援するという行為が、いかに人の心と身体を活性化させ、生きる力を与えるかを証明しています。同様の取り組みは、バスケットボールや野球など、他のスポーツにも広がりを見せています。
参考:大阪介護転職ネット「誰かを支えている実感が生きる力に変わる!高齢者にこそ「推し活」がおすすめ」参考:パラサポWEB「認知症のあるおばあちゃんがスペイン語に挑戦!? Jリーグの“推し活”が起こした数々の奇跡とは」参考:サントリーウエルネス株式会社「高齢者施設の利用者の幸福度が「推し活」とともに段階的に進展することを確認」
持続可能な「推し活×福祉」に向けて
 「推し活×福祉」は大きな可能性を秘めています。しかし、その持続的な発展のためには、いくつかの重要な壁を乗り越える必要があります。特に経済的自立と権利問題は、避けて通れない課題です。
「推し活×福祉」は大きな可能性を秘めています。しかし、その持続的な発展のためには、いくつかの重要な壁を乗り越える必要があります。特に経済的自立と権利問題は、避けて通れない課題です。
権利という壁:著作権・商標権とどう向き合うか
もう一つの重大な壁が、著作権や商標権、肖像権といった知的財産権の問題です。「推し活」の対象となるアイドル、キャラクター、スポーツチームのロゴなどは、すべて権利者によって保護されています。これらのデザインや写真を無断で商品化し、販売する行為は、たとえ非営利の福祉目的であっても法的に許されません。
個人のファンが趣味の範囲で二次創作を楽しむことは、権利者が黙認しているグレーゾーンに留まることが多いです。しかし、事業所が組織的にグッズを製作・販売するとなれば話は別です。著作権法には視覚障害者等のための複製を認める福祉的な例外規定がありますが、これは商品の販売を許可するものではありません。
この壁を乗り越える唯一の道は、権利者との正規のパートナーシップを構築することです。幸いにも「Be supporters!」の事例が示すように、JリーグやBリーグといった団体は社会貢献活動に積極的であり、協働の門戸を開いています。
今後は福祉事業所が権利者に対し、単なる「許諾」を求めるのではなく、「ファンの熱量を社会貢献に繋げる共同事業」として提案してライセンス契約を結ぶといった戦略的なアプローチが不可欠です。
参考:公益社団法人著作権情報センター「著作権が制限されるのはどんな場合?」参考:大阪府立中之島図書館「著作権法と障害者サービス」
持続可能な支援のために:企業と私たちにできること
「推し活×福祉」を持続可能なものにするためには、企業や個人の積極的な関与が欠かせません。企業、特にエンターテインメントやスポーツ関連の企業は、自社のIP(知的財産)やブランド力を活用したCSR活動として、福祉事業所との連携を深められます。
公式グッズの製作委託や、イベントへの招待、収益の一部を寄付するコラボレーション企画などが考えられます。企業の社会貢献だけでなく、ファンとのエンゲージメントを高め、ブランドイメージを向上させる効果も期待できるはずです。
私たち個人にできることも多いです。「にじげんマルシェ」のような事業所から商品を購入することは、単なる消費ではなく、作り手の経済的自立と自己実現を直接応援する「支援」となります。また「Be supporters!」に参加するチームを応援するのも、プロジェクトへの間接的な貢献です。
VR(仮想現実)やメタバースといった最新技術の活用も期待されます。外出が困難な重度の障害を持つ人でも、VRを通じて旅行を体験したり、メタバース空間でファンイベントに参加したりすることが可能です。これにより、支援の輪はさらに大きく広がっていきます。
まとめ
「推し活×福祉」は、現代の文化が持つポジティブなエネルギーを、長年の社会課題の解決につなげる画期的なアプローチです。障害のある人々を単なる「支援の対象」としてではなく、社会に価値を生み出す「主体的な存在」としてとらえ直す試みとなります。
「創る支援」は、彼らにプロフェッショナルとしての誇りと経済的自立への道を開き、「支える支援」は、生きる喜びと社会とのつながりを再発見させ、心と身体を元気にします。
これらのプロジェクトの目指す先は、支援者と被支援者という一方的な関係ではありません。選手とサポーター、作り手と買い手、アイドルとファンが互いに力を与え合う、「推し、推される」という相互的な関係性の構築にあります。
情熱が生きる力になり、消費が支援になります。この新しい循環が社会全体に広がったとき、私たちはだれもが自分の「好き」を誇り、互いを支え合う、よりインクルーシブで豊かな社会の実現に一歩近づけるのです。』
推し活という現代的な文化現象と、福祉という普遍的な社会課題が出会うことで生まれたこの新しいアプローチは、これからの共生社会のあり方を示す重要な指針となるに違いありません。
執筆者プロフィール
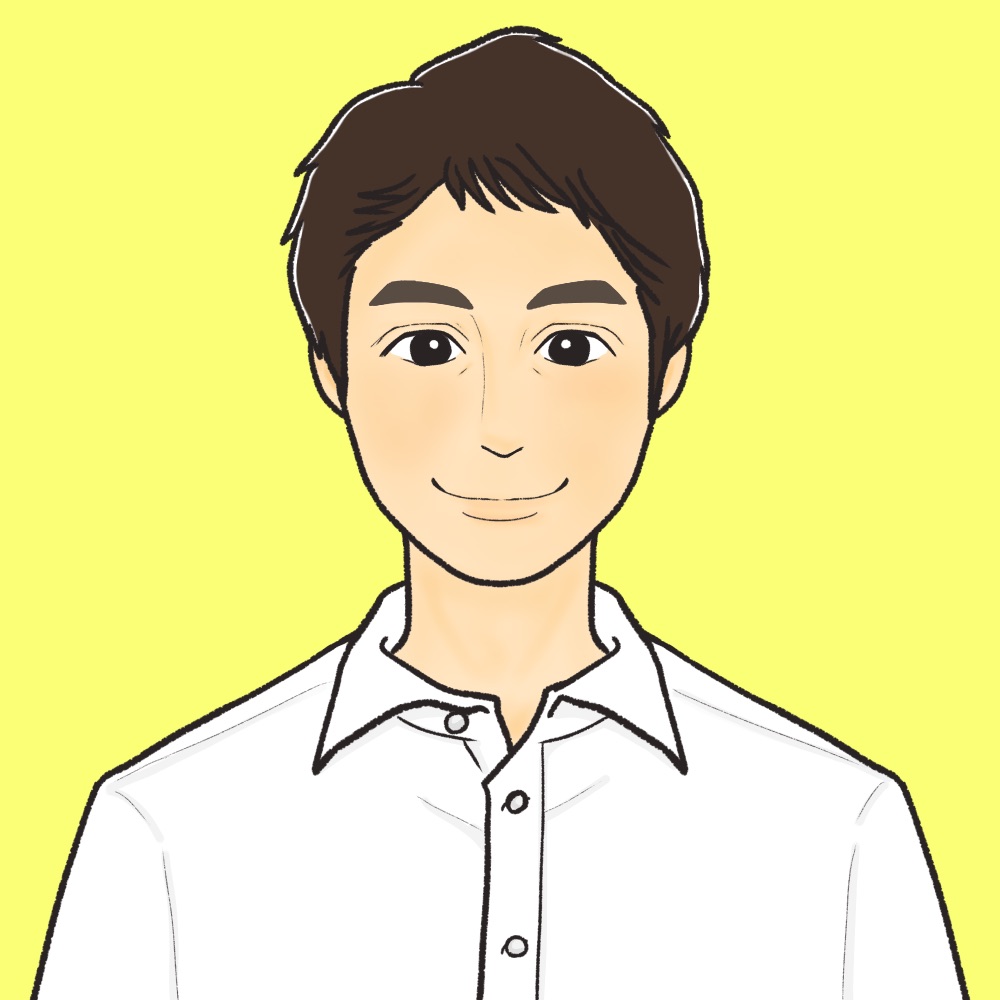
「情報は人を助ける力になる」をモットーに執筆活動を行うライター。
社会経験を活かし、消費者保護や労働法規の分野で独自調査を重ねている。得意分野は法制度や行政手続きのほか、キャリア形成論、ビジネススキル開発など。








