
「就労継続支援A型で働くと給料はどれくらいもらえるの?」
「生活できるだけのお金がもらえるんだろうか…」
「仕事はどんなことをするんだろう?」
就労継続支援A型の利用を考えているけれど、給料がどれくらいもらえるのか、生活が成り立つのか不安に感じている方も多いかもしれません。
この記事では、就労継続支援A型でもらえる給料についてわかりやすく解説しています。
就労継続支援A型を利用するメリットや選び方についても解説していますので、利用を検討している方は参考にしてください。
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型とは、一般的な企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づき継続的に働くことが可能な方に対して就労の場を提供する就労支援サービスです。
就労継続支援A型では、就労だけでなく、就労に必要な知識やスキルを身につけるためのトレーニングも受けられます。
就労継続支援A型の給料はどれくらいもらえる?
就労継続支援A型は、雇用契約をむすんで働くため最低賃金が保証されます。そのため、同じ就労支援サービスでも、雇用契約を結ばない就労継続支援B型より賃金は高い傾向にあります。
実際にどれくらいもらえるのか、平均月額給料や手取りの給料について詳しくみていきましょう。
就労継続支援A型の平均月額給料は?
厚生労働省の調査によると、2022年度における月額の平均給料は、83,551円です。
就労継続支援A型の月額の平均給料は、2014年から8年連続で増加傾向にあります。
今後も平均月額給料は上昇していく可能性があるといえるでしょう。
就労継続支援A型の手取りの給料は?
就労継続支援A型の手取りの給料は、働いて得た給料から社会保険料や利用料、交通費が差し引かれた金額です。
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、一定の要件を満たした場合には雇用保険などに加入します。
また、就労継続支援A型は、福祉サービスであるため所得によっては利用料が必要です。
事業所に通うための交通費もかかります。事業所によっては交通費の一部を支給してくれるところもあるようです。
利用料
就労継続支援A型の利用料は、国や県が9割を負担し、残りの1割を利用者が負担するしくみになっています。
また、利用者の所得によって負担上限額が定められており、それ以上の負担は生じません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 金額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
世帯の範囲は、本人と配偶者のみです。親や兄弟姉妹は、同居していても所得は考慮されません。
【参考】障害者の利用者負担|厚生労働省
雇用保険料
就労継続支援A型で週20時間以上働いた場合には、雇用保険に加入します。
令和6年度の労働者雇用保険料率は、0.6%です。給与額に0.6%(6/1000)をかけた金額が差し引かれます。
※雇用保険料率は、毎年見直されますので注意しましょう。
就労継続支援A型の給料は人それぞれ!モデルケースで解説

手取りの給料がどれくらいなのかイメージがわきにくいかもしれません。
ここでは、実際に、例を挙げて手取りの給料を計算してみます。
【東京都に住んでいるAさん】
週5日で6時間勤務をしています。利用料は9,300円です。
1,163円×6時間×20日-837円ー9,300円ー8,000円=121,423円
(時給×1日の勤務時間×勤務日数-雇用保険料-利用料-交通費)=手取りの給料
【秋田県に住んでいるBさん】
週5日で6時間勤務をしています。利用料は0円です。
951円×6時間×20日ー685円ー0円ー5,000円=108,435円
(時給×1日の勤務時間×勤務日数-雇用保険料-利用料-交通費)=手取りの給料
このように、東京都に住んでいるAさんと秋田県に住んでいるBさんでは最低賃金が異なります。
また、人によって利用料や交通費も異なるため、手取りの給料には個人差があります。
就労継続支援A型の手取りの給料は
によって金額が異なります。
就労継続支援A型の給料だけだと生活に不安を感じるときは?
就労継続支援A型の給料は、人それぞれ住んでいる地域や働く時間などにより異なります。
また、家族構成によっても生活に必要な金額は異なるでしょう。
「もう少し収入が欲しい」「生活にかかる費用をできるだけおさえたい」と考える方は多いかもしれません。
就労継続支援A型の給料だけでは不安だと感じたときには
- 障害者年金
- 自立支援医療
- 生活保護
などの支援制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
それぞれ解説していきます。
障害者年金
障害者年金は、病気やけがが原因で生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。
障害者年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けたときに、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を受け取れる可能性があります。
障害者年金を受給するには、障害の程度や年金の納付状況などの条件を満たす必要があります。
【参考】障害年金|日本年金機構
自立支援医療
自立支援医療は、心身の障害を軽減・除去するために必要な医療費の負担額を軽減してくれる制度です。自立支援医療には、精神通院医療と更生医療があります。
精神通院医療は、うつ病や統合失調症などの心の病を患っている方で、継続的な治療が必要な場合に、医療費の一部を公費で負担してくれます。
更生医療は、身体に障害のある方で、その障害を除去、軽減するための手術等の治療を受ける際に医療費の一部を公費で負担してくれる制度です。
【参考】自立支援医療制度の概要|厚生労働省
生活保護
生活保護は、世帯の収入が最低生活費に満たない方に対して保護費を支給する制度です。
保護費は、最低生活費から収入を引いた差額分が支給されます。
生活保護が必要だと認定されると、生活に必要な費用についてさまざまな扶助が支給されます。
就労継続支援A型で働きながら生活保護を受け取ることは原則可能です。もし、生活に困っている場合には、お住まいの自治体の相談窓口に相談してみるとよいでしょう。
【参考】生活保護制度|厚生労働省
就労継続支援A型を利用するメリット
就労継続支援A型を利用するメリットは、ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサポートが受けられることです。
一般的な会社に近い働き方ができる
就労継続支援A型では、一般的な会社に近い働き方ができます。
就労継続支援A型の事業所で行っている仕事内容は、以下の通りです。
- パンやお菓子などの製造
- レストランやカフェでの調理・接客
- パソコンを使った事務作業
- 清掃業務
- 農作業
- 商品の梱包・発送業務
- 手工芸品の製作
事業所によって従事する仕事は異なりますが、一般的な企業と同じように担当を任されて働きます。
体調に合わせて無理なく働ける
障害の程度や体調に合わせて無理なく働けるのもメリットです。
生活のリズムが整わずに悩んでいる場合には、資格を持った専門のスタッフに相談できます。
まずは、働くことに慣れたい、規則正しい生活がしたい方には、自分のペースで無理なく働けるでしょう。
就労継続支援A型事業所を選ぶ時のポイント

就労継続支援A型で働くと、最低賃金が保証された給料がもらえる、体調に合わせて無理なく働けるなどのメリットがあります。しかし、自分に合った事業所を選ばないと事業所に通うこと自体がつらくなってしまうでしょう。
ここでは、自分に合った事業所を選ぶときのポイントについて解説していきます。
仕事内容は自分に合っているか
就労継続支援A型の仕事内容は、事務や接客、軽作業など事業所によってそれぞれ異なります。
自分が興味のある仕事や体力に合った仕事を選ぶとミスマッチが起きにくくなります。
自分の特性などを振り返り、自分に合った仕事を選びましょう。
事業所の雰囲気どはうか
職場によって明るい雰囲気のところもあれば、落ち着いた雰囲気のところもあるでしょう。
職員の方や一緒に働く利用者の方との相性もあります。
事前に見学に行き、実際に働いている人の様子や事業所のスタッフとのやりとりなどから、自分に合っているかどうかよく確認するとよいでしょう。
お給料はどうか
就労継続支援A型の給料は最低賃金が保証されていますが、どれくらいの給料がもらえるかは事業所によって異なります。自分が納得できる金額がもらえるのか事前に確認しておきましょう。
通いやすい場所にあるか
事業所へのアクセスがよいか、自宅から通いやすい場所にあるかも確認しておくとよいでしょう。
事業所には基本的に毎日通うため、自宅から遠い場所やアクセスが悪い場所だと通うのが大変になってしまう可能性があります。
事業所によっては、交通費を一部支給してくれる場合もありますので確認しておくとよいでしょう。
まとめ
就労継続支援A型は、雇用契約を結ぶため最低賃金が保証された給料が支払われます。
厚生労働省の調査によると、2022年度の月額の平均給料は、83,551円です。
就労継続支援A型の給料だけだと収入が足りないと感じたときには、障害者年金や自立支援医療、生活保護などの支援制度の活用を検討してみるとよいかもしれません。
就労継続支援A型には、体調を考慮しながら一般的な会社と同じように働けるといったメリットもあります。また、就職に必要な知識やスキルを身につけるためのトレーニングも受けられます。
自分に合った事業所で働いて給料をもらいながら、体調や生活リズムを整えたり、一般企業への就職に向けて経験を積んだりするのもよいでしょう。
執筆者プロフィール
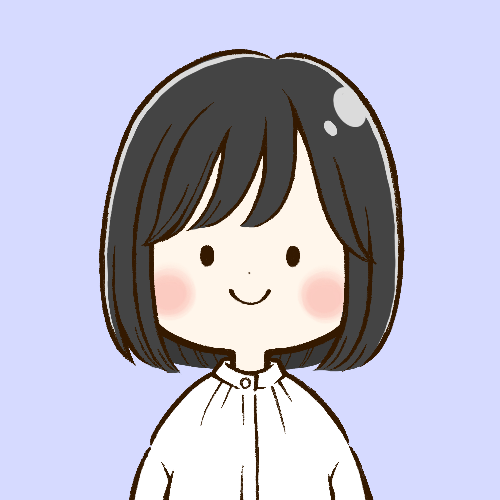
特別支援学校や小学校の特別支援学級に教員として勤務。さまざまな障害のある子どもとの関わりを経て、現在は、ライターとして福祉・教育を中心に執筆している。教員免許の他、保育士、社会福祉主事、手話検定2級の資格を保有。








