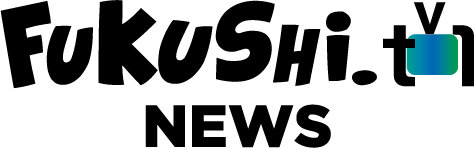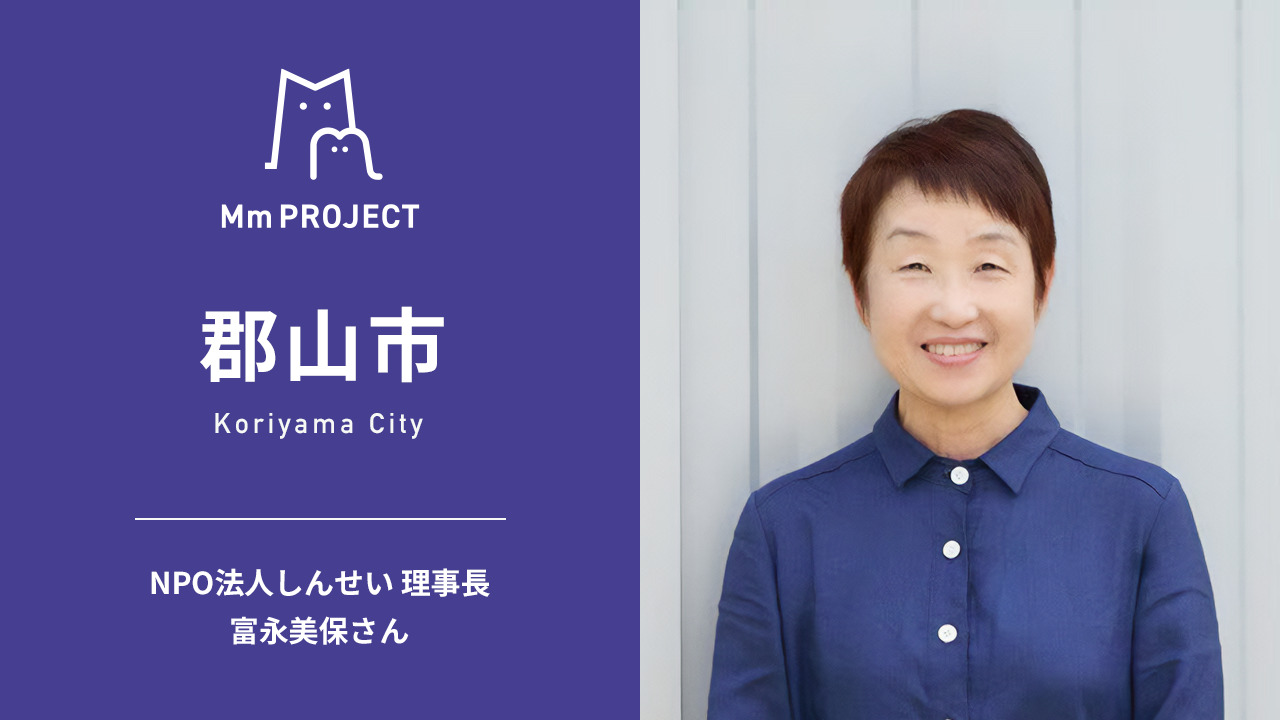
福祉.tvはこれまで、全国各地でさまざまな福祉の現場を取材してきました。その中で出会うのが「この人の語りは、活動そのものだ」と感じさせる存在です。
今回、MmPROJECT郡山セミナーで強く印象に残ったのが、NPO法人しんせい理事長・富永美保さんの言葉でした。障害者福祉、復興、仕事づくり、地域との関係。どのテーマを語っていても、そこにあったのは理念や正解ではなく、目の前の人と向き合い続けてきた時間でした。
福祉の話でありながら、特別なことをしているようには聞こえない。むしろ、暮らしや仕事、人生の延長線上に自然と置かれている。その感覚が、会場にいた多くの人の心に静かに残っていたように思います。
NPO法人しんせいとはどんな団体なのか、そして富永さんが何を考え、何を続けてきたのかを軸に、その歩みをたどります。
NPO法人しんせいのはじまり―制度の外で、人が集まった場所

NPO法人しんせいの原点にあるのは、2011年の東日本大震災と、それに続く原発事故です。突然、日常を奪われた人びとは、住み慣れた土地を離れ、避難生活を余儀なくされました。生活の基盤だけでなく、人との関係や役割、これまで積み上げてきた時間そのものが、いったん断ち切られるような状況でした。
富永さんがそこで目の当たりにしたのは「困っている」という事実がありながらも、制度の網からこぼれ落ちてしまう人たちの存在でした。障害者手帳の有無、支援対象かどうか、申請できるかどうか。そうした線引きの前に、明らかに孤立し、不安を抱え、居場所を失っている人がいました。
「誰かを支援したい」というよりも「この状況の中で、一緒にいられる場所が必要だ」しんせいの始まりは、そんな切実な感覚から生まれています。
当初、富永さんたちが行っていたことは、福祉事業でも、就労支援でもありませんでした。ただ集まり、話し、顔を合わせる。今日のことを話し、明日の不安を共有する。人が人として関係を保ち続けるための、極めてシンプルな営みです。
しかし、その「ただ一緒にいる」時間の中で、次第に見えてきたものがありました。それは、多くの人が「助けられる側」でいることに、強い違和感を覚えていたという事実です。
やがて、しんせいは障害福祉サービス事業所としての形を整えていきます。ただし、それは制度に合わせるためではなく、人の思いを受け止め続けるための「器」として制度を使うという選択でした。
制度の内側に入っても、しんせいは制度の論理に飲み込まれることはありませんでした。「これは制度上できない」ではなく「どうすれば、今ここにいる人が納得できるか」
この問いを、常に起点に置き続けてきたのです。
制度の外で人が集まり、その人たちの思いに引き寄せられるように、少しずつ制度が後から追いついてきた。
しんせいの成り立ちは、人と人が関係を手放さなかった時間の記録だと言えるでしょう。
「仕事がない」現実と「仕事がしたい」人たち

福祉事業として再スタートしたしんせいを待っていたのは、理想とはほど遠い現実でした。「働く場をつくる」と言葉にするのは簡単でも、実際に安定した仕事を用意することは容易ではありません。
「今日はやることがありません」
その言葉を口にすることが、どれほど重い意味を持つのか。富永さんは、その場面に何度も向き合ってきました。
利用者の多くは、「稼ぎたい」以上に、「誰かの役に立っている実感がほしい」と感じていました。
しかし、現実には一つの事業所だけで完結できる仕事には限界があります。大量の発注が来ても、人手や設備が追いつかず、断らざるを得ないこともありました。
その矛盾は、現場に大きなもどかしさを残します。
そこでしんせいが選んだのが「一つの事業所で抱え込まない」という発想でした。
複数の福祉事業所と連携し、仕事を分担する。
一人ひとりの得意な作業やペースに合わせて役割を割り振る。
そうして生まれたのが、「共同受注」という形です。
この仕組みは、単に作業効率を上げるためのものではありません。
そうした役割意識を一人ひとりが持てることが、何よりも大切にされていました。
富永さんが繰り返し語っていたのは「仕事の量」ではなく「仕事の質」です。工賃を上げることはもちろん重要ですが、それ以上に、仕事を通じて自分の存在が社会とつながっていると感じられるかどうかが問われていました。
その考え方は、しんせいが取り組んできたさまざまな仕事の形にも表れています。
たとえば、お菓子づくり。
クッキーや焼き菓子などの製造は、工程が細かく分かれており、計量、成形、包装、ラベル貼りと、一人ひとりが担える役割が明確です。「自分の作業が、次の工程につながっている」という実感が、仕事としての手応えを生んでいます。
また、クラフトの分野では、古着のデニムを再生したバッグや小物の製作に取り組んできました。素材選びから縫製、検品、販売まで、多くの工程を必要とするものづくりは、それぞれの得意な作業を活かしながら関われる仕事です。
近年では、ラグビーチーム「浦安D-Rocks」の公式グッズ制作にも携わりました。品質や納期が求められる仕事に関わることは「福祉だから」ではなく、一つの担い手として社会から信頼されているという実感につながります。
これらの仕事に共通しているのは、効率や成果を最優先するのではなく、一人ひとりが役割を持ち、関われる形をつくることでした。共同受注も、こうした考え方の延長線上にある手段の一つであり、しんせいの仕事づくりは、常に「人を中心に置く」ことから組み立てられています。
しんせいの仕事づくりは、効率や成果を最優先するものではありません。「ここに来てよかった」と思える時間を、仕事という形でつくり続けること。その姿勢こそが、しんせいの活動を支える原動力となっています。
山の農園という選択――もう一度、土地と関係を結び直す

しんせいの活動を象徴する場所の一つが、郡山市逢瀬町にある山の農園です。山の農園は、農業適格法人agrityとNPO法人しんせいが連携して取り組む、農福連携事業として運営されています。
ここは、単なる生産拠点ではありません。しんせいにとって山の農園は、失われた日常と、もう一度つながり直すための場所でもあります。
震災と原発事故によって、多くの人が住み慣れた土地を離れることになりました。戻れない場所が生まれた一方で、「どこで生き直すのか」という問いが、避けられない形で突きつけられます。
富永さんたちは、その問いに対して、「新しい土地で、もう一度関係を築く」という選択をしました。山の農園は、その象徴です。
農業は、効率や成果がすぐに見える仕事ではありません。天候や土の状態に左右され、思うようにいかない日も多い。それでも、土に触れ、季節の移ろいを感じながら身体を動かす時間は、人の感覚を少しずつ取り戻していく力を持っています。
しんせいにとって農園は、収益を上げるためだけの場所ではありませんでした。
朝、畑に出る理由があること。
仲間と声を掛け合いながら作業をすること。
その積み重ねが、生活のリズムをつくり、人と人の距離を縮めていきます。
また、山の農園を始めるにあたっては、安全性への不安とも向き合う必要がありました。富永さんたちは、国立環境研究所などの専門機関と連携し、放射線量の測定や土壌の確認を重ねながら、自分たちが納得できる形で農業を続ける道を選びます。
「大丈夫だと言われたから」ではなく、「自分たちが確かめ、理解したうえで続けられること」
この姿勢は、しんせいのすべての活動に共通しています。
山の農園は、過去を取り戻すための場所ではありません。これからの時間を、ここで積み重ねていくための場所です。
この農園で育った作物は、やがて仕事になり、商品になり、社会へとつながっていきます。
その最初の一歩として、山の農園は、しんせいの実践の中心にあり続けています。
山のにんじんカレーという“物語”

山のにんじんカレー物語02〜循環編〜山のにんじんカレー物語03〜エネルギー編〜山のにんじんカレー物語04〜共生編〜山のにんじんカレー物語05〜備災編〜
「山のにんじんカレー」は、しんせいの活動を象徴する商品として知られています。しかし、このカレーは、最初から“商品をつくろう”として生まれたものではありません。
そこにあったのは、仕事をつくりたいという思いと、この土地で生きてきた時間を、何かの形で残したいという願いでした。
山の農園で育てられたにんじんは、見た目がそろっているわけでも、効率よく大量生産できるものでもありません。それでも、土に触れ、季節を感じながら育てたにんじんには、確かな手応えがありました。
「このにんじんを、どうやったら“仕事”にできるだろうか」
その問いから、試行錯誤が始まります。
“売れるもの”ではなく、“つくり続けられるもの”を
商品開発にあたって、富永さんたちが最初に考えたのは、「流行るかどうか」ではありませんでした。一時的に話題になる商品ではなく、長くつくり続けられること。そして、つくる人が誇りを持てること。
そうして選ばれたのが、「カレー」という形でした。
誰にとってもなじみがあり、特別な知識がなくても手に取れる。一方で、素材や作り方次第で、しっかりと個性を表現できる。山のにんじんの甘みや旨みを、そのまま活かすことができる料理でもあります。
震災の経験が、味と設計に息づいている
山のにんじんカレーは、国産原料を中心に使用し、油分を抑えたやさしい味わいが特徴です。そこには、東日本大震災と原発事故を経験したしんせいならではの視点があります。
避難生活の中で、
「食べられるものがある」
「体に負担をかけずに口にできるものがある」
その安心感が、どれほど大きかったか。
山のにんじんカレーは、防災食としての側面も意識して設計されています。非常時でも食べやすく、日常でも無理なく食べ続けられる。その“二重の意味でのやさしさ”が、このカレーの根底にあります。
パッケージに込めた、「語られない時間」

山のにんじんカレーのパッケージは、決して派手ではありません。しかし、そこには「説明しすぎない」美しさがあります。
誰がつくったのか。どんな場所で生まれたのか。それをすべて言葉で語らなくても、背景にある時間が、静かににじむように設計されています。
富永さんは、商品について語るとき「かわいそうだから買ってほしい」とは決して言いません。むしろ、「おいしいと思ったら、また選んでほしい」と語ります。
それは、しんせいが目指している関係性そのものです。支援する側とされる側ではなく、つくる人と、選ぶ人として出会うこと。
社会とつながる一場面としてのセミナー

今回のMmPROJECT郡山セミナーで、山のにんじんカレーは、郡山市の地産事業におけるふるさと納税返礼品第一号として紹介されました。
寄付者が選び、事業所がつくり、その対価が利用者の工賃になる。この当たり前の循環が、制度として形になった瞬間です。
セミナーでは、試食を通じて参加者が商品を手に取り、背景にある物語に耳を傾けました。「おいしい」という感想とともに、「この選択が、誰かの仕事につながっている」という実感が共有されていきます。
それは、しんせいがこれまで積み重ねてきた実践が、社会と接続した一場面でした。
福祉の力を、街の力へ

富永さんが見据えているのは、特別な成功や拡大ではありません。障害のある人の仕事やものづくりが、「支援」ではなく、街の当たり前の営みとして存在すること。
誰かが応援しなければ成り立たないのではなく、誰かが自然に選び、手に取り、関わっていく。しんせいの歩みは、その状態を現実にするための、地道で誠実な実践です。
福祉の力は、すでに街の中にあります。それをどう結び、どう循環させていくのか。富永美保さんとNPO法人しんせいの活動は、その問いに対する一つの確かな答えを、私たちに示してくれています。
Rethink PROJECTについての詳しい情報は「https://www.rethink-pjt.jp」にてご確認いただけます。
写真提供:NPO法人しんせい撮影:福祉.tv編集部
執筆者プロフィール

福祉サポートをしていただく企業の取り組みや、福祉を必要とする方々の活躍の様子など、福祉に関わる多様な情報を紹介しています。