 日本の高齢化率が29.1%に達する中、高齢者や障がいのある人々の旅行ニーズが急拡大しています。
日本の高齢化率が29.1%に達する中、高齢者や障がいのある人々の旅行ニーズが急拡大しています。
本記事では「旅行をあきらめる層」という巨大な潜在市場を掘り起こす「旅する福祉」の最新動向を解説し、この成長市場の可能性を探っていきます。ぜひ最後までご覧ください。
「旅する福祉」の概念と市場の現状
 日本が世界のどの国も経験したことのない速度で超高齢社会へと突き進む中、新たな成長市場として注目を集めているのが「旅する福祉」の分野です。
日本が世界のどの国も経験したことのない速度で超高齢社会へと突き進む中、新たな成長市場として注目を集めているのが「旅する福祉」の分野です。
ここでは、高齢者や障がいのある人々の「旅したい」という願いを現実に変える「旅する福祉」の最新動向を解説します。
ユニバーサルツーリズム
ユニバーサルツーリズムは、観光庁が推進する「高齢や障がいなどの有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行」を目指す包括的な理念です。特定の層を対象とするのではなく、健常者を含むすべての人々にとって利用しやすい環境とサービスの整備を目指しています。
日本の構造的な人口動態の変化により、この取り組みの重要性は増しています。2023年10月時点で65歳以上人口の割合は29.1%に達しました。2040年には34.8%、2070年には39%に達すると予測されています。これは国民の2.6人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上という社会の到来を意味します。
バリアフリー旅行
バリアフリー旅行は、旅行の過程に存在するさまざまな「バリア(障壁)」を取り除くことに焦点を当てた旅行形態です。具体的には以下の4つのバリアがあります。
物理的バリア:段差、狭い通路、不適切な設備など
制度的バリア:利用制限、不適切なルールなど
文化的・情報的バリア:言語の壁、案内の不足など
心理的バリア:周囲への気兼ね、偏見など
興味深いことに、70代以上の高齢者の旅行回数は60代のピーク時(年間1.62回)から1.13回へと急減しています。この「旅行断念層」は年間約1000万回、経済効果約5000億円という巨大な潜在市場を形成しています。
介護(介助)付き旅行
介護付き旅行は、高齢者や障がいのある方に対する人的支援に特化したサービス分野です。
単なる移動補助に留まらず、旅行プランの作成から交通機関や宿泊施設の手配、当日の添乗、食事・入浴・排泄といった介護ケア、さらには医療的ケアまでを含む、極めて個別性の高いオーダーメイド型サービスとなっています。
バリアフリー旅行を支えるサービスプロバイダー
 1990年代から市場を開拓してきたパイオニア企業から、地域に根ざした支援拠点まで、多様なサービスプロバイダーがそれぞれ独自の戦略でこの成長市場に参入し、競争と協力を通じて業界全体の発展を牽引しています。
1990年代から市場を開拓してきたパイオニア企業から、地域に根ざした支援拠点まで、多様なサービスプロバイダーがそれぞれ独自の戦略でこの成長市場に参入し、競争と協力を通じて業界全体の発展を牽引しています。
ここでは、サービスプロバイダーの具体的な事業内容と戦略を詳しく分析し、この新しい市場の構造と発展可能性を明らかにします。
「トラベルヘルパー」という選択肢
トラベルヘルパーは、介護技術と旅行業務知識を兼ね備えた「外出支援の専門家」として定義されます。その最大の特徴は、利用者一人ひとりの身体状況や希望に応じてオーダーメイド型のサポートを提供することです。
サービス範囲は近所の買い物や墓参りといった日常的な外出から、温泉旅行、海外旅行まで多岐にわたります。看護師資格を持つトラベルヘルパーが同行すれば、インスリン注射や経管栄養、吸引といった医療的ケアにも対応可能です。
主要事業者の戦略分析
あ・える倶楽部は1990年代から介護旅行事業を手掛けるパイオニアで、全国約750名のトラベルヘルパーを擁しています。大手旅行会社との提携で、2014年にJTBグループと業務提携し、ANAやJALとも連携を拡大しています。
料金体系は、利用者の介護度に応じた基本料金(中度要介護者の場合1日8時間で38,700円)をベースに、夜間介助やオプションを加えた構成です。
日本介護トラベルサービスは高齢者や車椅子利用者に特化し、有馬温泉1泊2日の3名旅行で合計296,700円(一人あたり98,900円)といった具体的な料金事例を明示するなど、価格の透明性を重視しています。
伊勢志摩バリアフリーツアーセンターは、全国展開型とは異なる地域密着型のアプローチで注目されています。その活動は単一の旅行サービス提供に留まらず、地域全体の受入環境向上を目指す「まちづくり」の視点を持っています。
徹底した当事者視点での情報収集・発信、ワンストップの相談・手配機能、地域への積極的な働きかけによる環境整備など、多角的な取り組みを展開しているのが特徴です。設立当時9施設10室だった伊勢志摩地域のバリアフリールームは、19施設25室へと倍増するなど着実な成果を上げています。
立ちはだかる多層的なバリア
 高齢者や障がいのある人々が旅行を断念する背景には、単一の理由ではなく、物理的・情報的・心理的・経済的な4つのバリアが複雑に絡み合った構造的な問題が存在します。
高齢者や障がいのある人々が旅行を断念する背景には、単一の理由ではなく、物理的・情報的・心理的・経済的な4つのバリアが複雑に絡み合った構造的な問題が存在します。
これらの多層的なバリアは相互に影響し合い、一つを解決しても他のバリアが残存する限り、真の意味での「旅する福祉」の実現は困難な状況にあります。
物理的バリア
宿泊施設においては課題が山積しており、海外からの障がいのある旅行者を対象とした調査では「宿泊施設にアクセシブル・ルーム(誰でも安心して使えるように工夫されたバリアフリーの部屋)が少ない・ない」が50.0%と最大の不満点として挙げられています。特に日本の伝統的な温泉旅館では、館内の段差や階段、部屋風呂や貸切風呂の構造が大きな障壁となっています。
交通機関では「エレベーターがない駅や、電車の乗降で課題がある」との声が多く、観光地では約7割の海外在住障がい者が「車いすでのアクセスが困難」という先入観を抱いているのが現状です。
情報のバリア
物理的バリア以上に深刻なのが「情報のバリア」です。障がいのある人の旅行を支援する家族や介助者は「バリアフリー情報がない、もしくは不十分」であることに最も困難を感じています。また、旅行会社の66.7%が「バリアフリーに対応している観光施設の情報が不足・不充実で商品を造成できない」と回答しています。
重要なのは、単なる「バリアフリー対応」の表記ではありません。「入口の幅は何cmか」「段差は何段で、高さは何cmか」といった、自身の能力で乗り越えられるかを判断するための具体的で詳細な情報です。
心のバリア
「心のバリアフリー」とは、物理的対応だけでなく、障がいや多様性に対する偏見や固定観念といった「意識上のバリア」を取り除くことです。当事者が抱える「周りに迷惑をかけてしまうのではないか」という気兼ねや、事業者側の「どう対応してよいかわからない」という戸惑いが、旅行への一歩を阻んでいます。
観光庁の「心のバリアフリー認定制度」は、この課題解決を目指しています。しかし、現状では86.6%もの施設が認定を取得しておらず、制度の認知度向上が課題です。
経済的バリア
障がいのある人がほとんど旅行に行かない最大の理由として「旅行商品の料金が高い」(64.7%)が挙げられています。介助付き旅行では、本人の旅費に加えてトラベルヘルパーの費用(1日3万円〜4万円程度の日当、交通費、宿泊費など)が上乗せされ、健常者の旅行に比べて大幅に高額になります。
公的支援には限界があり、障がい者総合支援法などの外出支援サービスは通院や買い物といった日常生活範囲での利用を想定しているため、観光目的での利用は原則として対象外です。
課題解決に向けた国家的アプローチ
 多層的なバリアに対し、国や地方自治体は法制度の整備や財政支援、ソフト面の取り組みを通じて、その解消に本格的に乗り出しています。
多層的なバリアに対し、国や地方自治体は法制度の整備や財政支援、ソフト面の取り組みを通じて、その解消に本格的に乗り出しています。
特に2024年の改正障がい者差別解消法施行により民間事業者の「合理的配慮」が法的義務化されるなど、政策的アプローチは新たな段階に入っています。
国の政策動向
観光庁が実施する「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」は、宿泊施設や観光施設のバリアフリー化に取り組む際の施設整備や設備導入にかかる経費の一部を補助する直接的な財政支援策です。
補助率は対象経費の1/2で、補助上限額は事業規模によって異なります。
大規模枠(事業費1500万円以上):防災協定締結の宿泊事業者は3000万円、その他は1500万円
小規模枠(事業費1500万円未満):750万円
特に災害時に避難者を受け入れる宿泊事業者を手厚く支援する姿勢は、ユニバーサルツーリズムと観光防災を一体的に推進する戦略の表れです。
法制度のインパクト
2024年4月1日に施行された改正障がい者差別解消法により、これまで努力義務であった民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。これは、宿泊施設などに対し、個々の状況に応じた柔軟な対応を法的に求めるものです。
具体的な配慮例として以下が挙げられます。
車いす利用者のためのスロープ板設置
聴覚障がい者への筆談対応
知的・発達障がい者への配慮した部屋変更 など
一方で、過重な負担(長時間の身体介助など)は提供義務はないとされており、事業者と利用者の権利のバランスを取る配慮もなされています。
まとめ
「旅する福祉」は、日本の超高齢社会という構造的変化を背景に生まれた巨大な潜在市場です。約5000億円の経済効果が見込まれるこの市場の開花には、物理的、情報的、心理的、経済的な多層的バリアの解消が不可欠です。
事業者には、社会モデルへの思考転換と心のバリアフリー認定制度の戦略的活用、テクノロジーを活用した情報発信の充実が求められます。政策立案者には、ハード・ソフト・ヒューマンウェア支援の三位一体改革と、観光と福祉の制度的連携強化が必要です。
「旅する福祉」の推進は、単なる新しい旅行形態の提案ではありません。それは、誰もが尊厳を持って生きることができる共生社会実現に向けた重要な試金石であり、日本の観光産業と社会全体のより豊かで持続可能な未来への力強い推進力なのです。
執筆者プロフィール
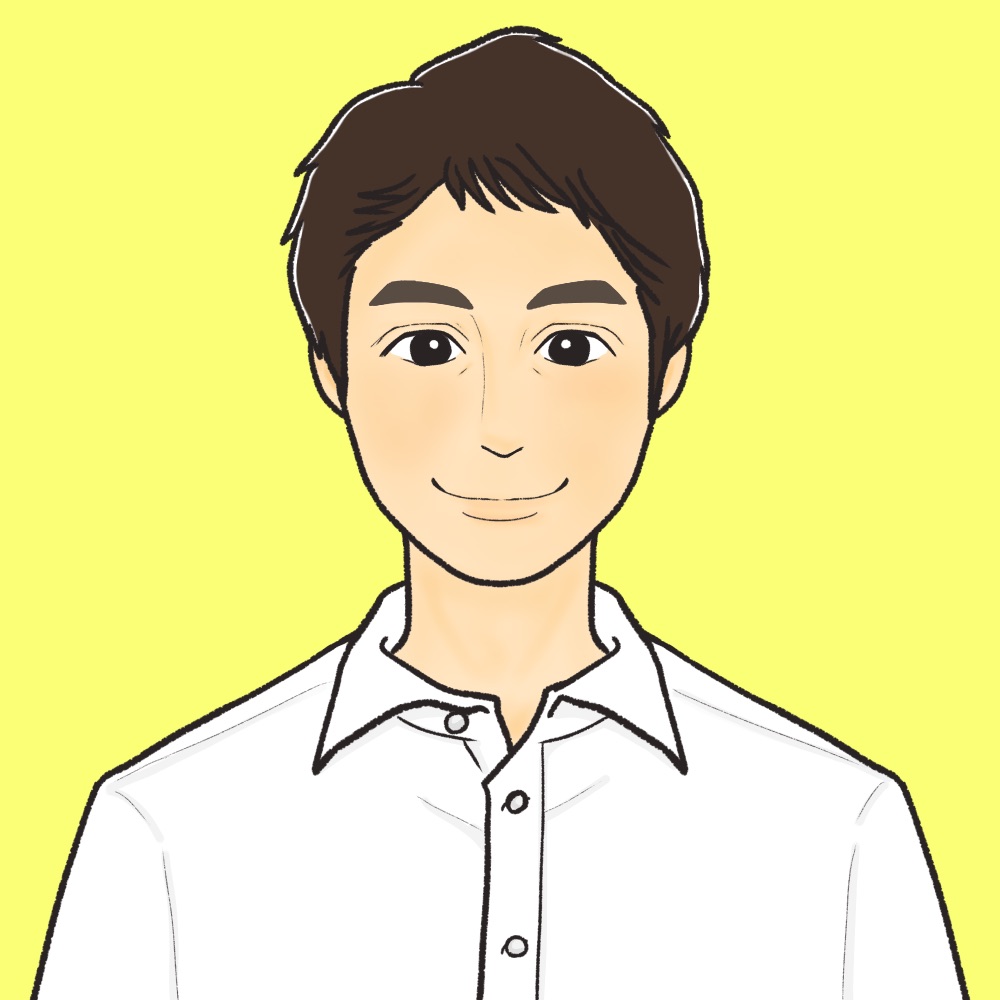
「情報は人を助ける力になる」をモットーに執筆活動を行うライター。
社会経験を活かし、消費者保護や労働法規の分野で独自調査を重ねている。得意分野は法制度や行政手続きのほか、キャリア形成論、ビジネススキル開発など。








