 高齢化社会の進展と共生社会への意識の高まりを背景に、車椅子技術は大きな変革期を迎えています。従来の平坦な路面での移動補助という概念を超え、階段昇降や不整地走破能力、革新的な操作インターフェースを備えた次世代車椅子の開発が加速しているためです。
高齢化社会の進展と共生社会への意識の高まりを背景に、車椅子技術は大きな変革期を迎えています。従来の平坦な路面での移動補助という概念を超え、階段昇降や不整地走破能力、革新的な操作インターフェースを備えた次世代車椅子の開発が加速しているためです。
「100m先のコンビニに行くのをあきらめる」という利用者の切実な声に応え、物理的・心理的障壁を取り除き、活動範囲と可能性を広げる高度な移動支援機器へと進化しています。本記事では、この分野における最新技術動向と、実用化に向けた課題、そして未来への展望を詳細に解説します。
高度な移動支援機器への進化
 従来の車椅子は、移動能力に制約のある人々にとって不可欠なツールであり続けてきました。しかし、その機能は主に平坦な環境での移動補助に限定され、階段や不整地といった日常的な障壁は利用者の活動範囲を依然として制限してきました。
従来の車椅子は、移動能力に制約のある人々にとって不可欠なツールであり続けてきました。しかし、その機能は主に平坦な環境での移動補助に限定され、階段や不整地といった日常的な障壁は利用者の活動範囲を依然として制限してきました。
近年「100m先のコンビニに行くのをあきらめる」といった利用者の切実な声に後押しされ、これらの限界を克服しようとする技術開発が活発化しています。車椅子は単なる移動手段から利用者の活動範囲を積極的に拡大し、生活の質(QOL)を向上させるための高度な移動支援機器へと進化を遂げつつあります。
進化の背景にあるのが、世界的な高齢化の進展や、共生社会実現に向けたバリアフリー化への意識の高まりです。特に日本では高齢者人口の増加に加え、障害者の高齢化も進んでおり、より高性能で多様なニーズに応えられる移動支援機器への需要は増大しています。こうした社会的要請が、次世代車椅子の研究開発を加速させる大きな要因です。
次世代を駆動する主要な技術的進歩
 次世代車椅子の進化は、いくつかの核となる技術分野によって牽引されています。これらの技術は、従来の車椅子が直面していた物理的、操作的な制約を打破し、利用者の可能性を大きく広げることを目指しています。
次世代車椅子の進化は、いくつかの核となる技術分野によって牽引されています。これらの技術は、従来の車椅子が直面していた物理的、操作的な制約を打破し、利用者の可能性を大きく広げることを目指しています。
階段・エスカレーター昇降技術
車椅子利用者にとって最大の物理的障壁の一つである階段を克服する技術は、次世代車椅子の象徴的な機能として注目されています。スイスで開発中の「Scewo」は車輪の内側にクローラー(履帯)機構を搭載し、セルフバランシング技術と組み合わせることで、車体を水平に保ちながら安定した階段昇降を実現します。
日本のLIFEHUB社が開発する「AVEST」も同様です。クローラー機構と独自の重心制御システムにより、最大40度の傾斜での階段昇降を目指しています。これらのシステムは、階段だけでなく、エスカレーターへの対応も視野に入れて開発が進められています。
階段昇降機に組み込まれているのは、昇降角度の変化に対応して機体を自動制御する機能や、緊急時に安全に停止・下降させる電磁ブレーキシステムなどです。
しかし、これらの高度な機構は、技術的な複雑さ、安全性確保の難しさ、コストや重量といった課題を伴います。Scewoは2019年末の実用化を目指していましたが、その後の状況は不透明です。
LIFEHUBは2026年の発売開始を予定し、安全性実証を進めています。階段昇降技術は、まだ研究開発段階や市場導入初期のものが多く、一般への普及にはさらなる技術成熟とコスト低減が必要です。
不整地踏破・障害物回避能力
日常生活における移動は、必ずしも平坦で整備された道ばかりではありません。砂利道、芝生、雪道などの不整地や、予期せぬ段差への対応能力も、次世代車椅子の重要な要素です。4輪駆動(4WD)システムは、砂地や湿地、滑りやすい路面での安定した走行が可能です。また、ゴムクローラーを採用することで、未舗装路面での踏破能力を高める方法もあります。
WHILL社が採用するオムニホイール(全方位タイヤ)は、複数の小さな樽型ローラーを組み合わせた特殊なタイヤです。その場で旋回できるほどの小回り性能(最小回転半径約76cm)と、ある程度の段差(最大5cm〜7.5cm)や悪路を乗り越える走破性を両立させています。これは、特に屋内や狭い場所での利便性を大きく向上させます。
乗り心地の向上も重要です。路面の凹凸や段差越え時の衝撃を吸収するため、先進的なサスペンションシステムが開発されています。さらに、安全性を高めるために、自動車の衝突防止システムを応用した障害物検知センサーや衝突回避システムの搭載も進行中です。これらの技術は、利用者がより多様な環境へ、安全かつ快適にアクセスすることを可能にします。
環境適応技術の開発は、車椅子を単なる「移動補助具」から、利用者の活動範囲を積極的に広げる「パーソナルモビリティ」へと進化させる上で中心的な役割を担っています。しかし、特に階段昇降のような高度な機能は、依然として技術的な複雑さやコストが普及の障壁です。現時点ではまだ限定的な利用に留まっています。
その一方で、不整地走行や小回り性能、安全性向上技術は、市販モデルにも徐々に搭載されつつあり、より現実的な進化として利用者の利益につながり始めています。
革新的な制御インターフェース:ハンズフリーとその先へ
 重度の肢体不自由を持つ人々にとって、従来のジョイスティック等による操作が困難な場合があります。次世代の制御インターフェースは、脳波、視線、その他の生体信号を利用し、より直感的で負担の少ない、あるいはハンズフリーでの操作を目指しています。
重度の肢体不自由を持つ人々にとって、従来のジョイスティック等による操作が困難な場合があります。次世代の制御インターフェースは、脳波、視線、その他の生体信号を利用し、より直感的で負担の少ない、あるいはハンズフリーでの操作を目指しています。
ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI):可能性と障壁
BCIは脳活動を読み取り、それをコンピュータや外部機器へのコマンドに変換する技術です。思考だけで車椅子を操作するという究極のインターフェースとして期待されています。BCIには、脳に電極を埋め込む「侵襲型」、頭皮上から脳波(EEG)などを計測する「非侵襲型」、その中間に位置する「部分的侵襲型」があります。
非侵襲型(特にEEG)は、手術が不要で比較的安価なため研究が盛んです。しかし、頭蓋骨などの影響で信号品質が低く、外部ノイズの影響を受けやすいのが課題です。研究レベルでは、EEGに加えて筋電位(EMG)や眼電位(EOG)を組み合わせ、特定のジェスチャー(例:奥歯を噛む、眉間にしわを寄せる)を認識して車椅子を制御する試みも行われています。しかし、現状では認識できるコマンドの種類が限られたり、意図しない動作を防ぐための安全策が必要だったりします。
侵襲型は、脳活動を直接捉えるため信号品質は高いです。ただし、外科手術のリスクや長期的な生体適合性、倫理的な問題が伴います。部分的侵襲型は、これらのリスクを低減しつつ信号品質を高めることを目指しますが、依然として侵襲的な処置が必要です。
BCIの実用化における最大の課題は、その信頼性と精度、そして安全性です。実験室でのデモンストレーションは進んでいますが、実環境で多様な状況に対応し、利用者の意図を正確かつ安定的に読み取り、安全に操作を実行するには、まだ多くの技術的ハードルが存在します。
例えば、「停止」コマンドの失敗は重大な事故につながりかねません。また、「ゆっくり進む」「注意して曲がる」といった微妙なニュアンスを伝えることも現状では困難です。
視線追跡・注視ベース制御
眼球運動は麻痺の影響を受けにくい場合が多く、視線や顔の向きを利用した操作も有望なハンズフリーインターフェースです。タブレット端末のカメラなどで視線や顔の向きを検出し、その方向へ車椅子を動かす仕組みが研究されています。メリットとしては、直感的な操作が可能であること、手を使わずに済むことです。
しかし、ここでも課題があります。「MidasTouchProblem」と呼ばれるもので、移動したい方向を見る意図的な視線だけでなく、周囲を確認するための無意識的な視線や顔の動きまで操作として誤認識してしまう問題です。
この問題を解決するため、視線の動きのパターンや時間的変化をAI(LSTMやCNNなど)で解析し、利用者の真の意図を推定する研究が進められています。それでも、「停止」や「特定の対象物への注視」といった多様な状態を正確に識別し、安全な制御を実現するには、さらなる精度向上が求められています。
まとめ
次世代車椅子技術は、単なる移動手段から利用者の生活の質を積極的に向上させる高度な移動支援機器へと進化しています。Scewoや日本のAVESTに代表される階段昇降技術、WHILLのオムニホイールによる小回り性能と段差克服能力、BCIや視線追跡による革新的操作インターフェースなど、多岐にわたる技術開発が進行中です。
しかし、これらの技術は安全性の確保、信頼性向上、コスト削減という共通課題に直面しています。特に階段昇降や脳波制御といった高度な機能は、まだ研究開発段階や市場導入初期の段階にあり、広く普及するためには更なる技術的成熟が必要です。
一方で、不整地走行や障害物回避機能などは、すでに一部の市販モデルに搭載され始めており、より現実的な進化として利用者の日常生活を着実に改善しています。高齢化社会の加速と技術革新の融合により、車椅子はこれからも進化を続け、利用者の活動範囲と可能性をさらに広げていくでしょう。
移動の自由は基本的人権の一つであり、次世代車椅子技術はその実現に大きく貢献することが期待されています。
参考)
WHILLが最新テクノロジーで追求する次世代のパーソナル モビリティとは
〈2027年IPO準備開始〉バリアフリーを自ら創る“22世紀の車いす”で世界中の人に移動の自由を「LIFEHUB」
超高齢社会で需要が高まる介護・福祉用具のレンタルサービス。SDGsの目標達成と環境配慮で社会に貢献
デザイン思考を基にした支援機器の開発・事業化を実現するためのガイドブック
真のニーズに基づく支援機器の開発・事業化を実現するための出口・普及を想定した支援ネットワークモデル構築のための研究
令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(福祉用具開発事業の方向性に関する調査)
BWSCストーリーズ
株式会社サンワ|企業情報
株式会社サンワ|福祉用階段昇降機
スイスの大学から生まれた、階段走行を可能にした車椅子「Scewo」
第38回 国際福祉機器展 – RIBA-IIやHOSPI-Remoなどが登場
次世代型車いす「WHILL」
外出が楽しくなる電動車いす スタンダードモデル発売で普及拡大
パリミキが次世代型車椅子・WHILLを取り扱う理由
WHILL株式会社|開発秘話
BMI 型生活環境制御装置の小型化と 実証評価に関する研究開発
BCI(ブレイン・コンピューター・インターフェース)入門:脳と機械をつなぐ最新技術と未来
科学研究費補助金研究成果報告書
念じるだけ…「脳波」で動く電動車いすが開発される! 操作の精度を99%以上に高めることに成功
G-TeC報告書「ブレイン・マシン・インターフェース」(米国)
目的地を思い浮かべるだけで車いすが自律的に走行。
中沢研究室が脳波を用いた車いすロボット制御システムを開発
令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(福祉用具開発事業の方向性に関する調査)
執筆者プロフィール
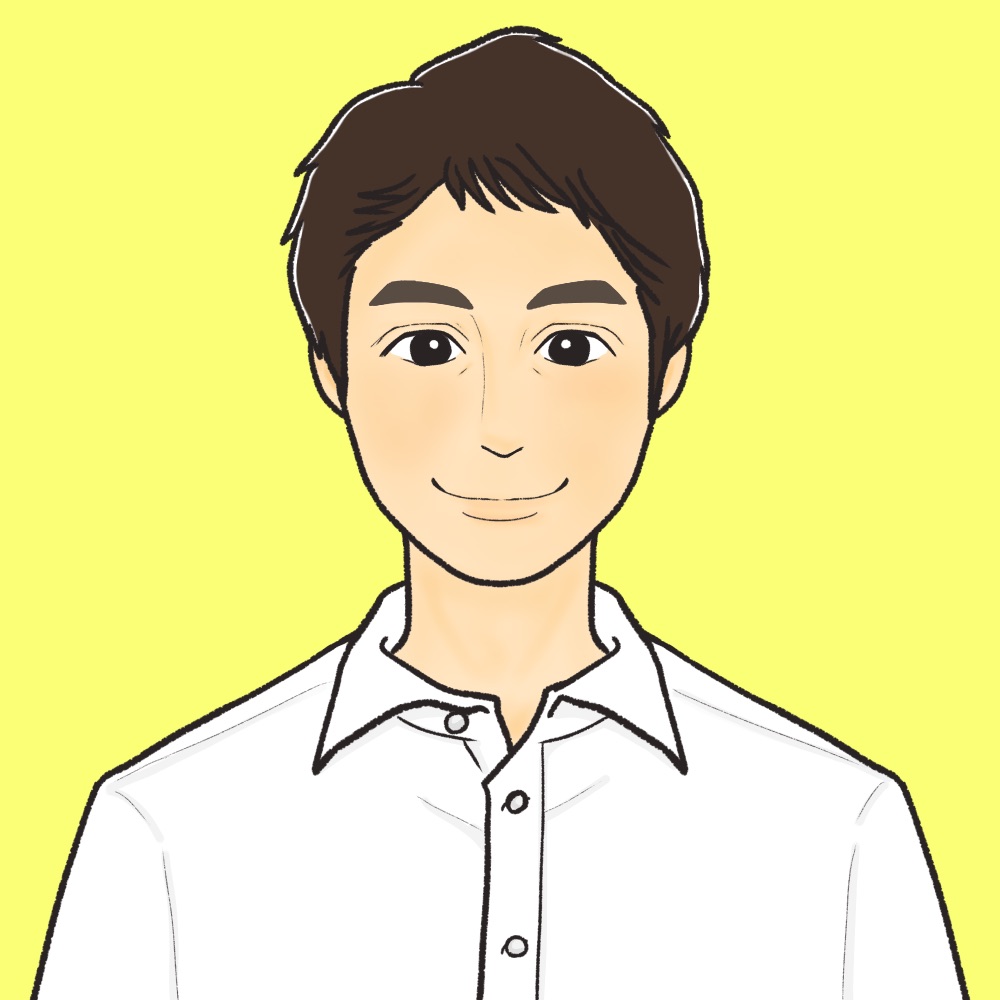
「情報は人を助ける力になる」をモットーに執筆活動を行うライター。
社会経験を活かし、消費者保護や労働法規の分野で独自調査を重ねている。得意分野は法制度や行政手続きのほか、キャリア形成論、ビジネススキル開発など。








