 「てんかん発作があった時はどうすればいいの?」
「てんかん発作があった時はどうすればいいの?」
「生活でどんなサポートをしてあげたらいいのかわからない」
と悩んでいる方も多いでしょう。
てんかんは、脳細胞に過剰な電気信号が起こることにより発作が起こる脳の病気です。意識を失う、体の一部がガクガクするなどの症状があらわれます。急に発作が起きる場合も多く、周りからびっくりされてしまうことも少なくありません。
この記事では、てんかんの原因や症状についてご紹介します。てんかんが起きたときの対処法や生活するうえで気をつけることについても解説していますので参考にしてください。
てんかんとは?
てんかんとは、脳の神経細胞に過剰な電気が発生する性質により、発作を繰り返す脳の病気です。
脳には無数の神経細胞がはりめぐらされ、神経の中を電気信号が通ることで、さまざまな情報を処理しています。脳内の神経細胞の電気信号によるやりとりによって、思考やコミュニケーション、感情などの精神活動が行われているのです。
しかし、何らかの原因で過剰な電気が起こると、突然意識を失ったり、筋肉が硬直したりするなどのてんかん発作となってあらわれます。
てんかんの原因
てんかんの原因は、大きく分けると、症候性と特発性の2つに分類されます。
症候性は、脳に何らかの病気があることが要因でてんかん発作をおこすものです。例えば、出生時の仮死状態による低酸素や脳の外傷などが原因として挙げられます。
特発性は、脳の外傷や障害など明らかな原因が認められないにも関わらず、てんかん発作を繰り返している状態です。
特に、子どものてんかんは原因がはっきりしない場合が多いです。
てんかんの症状
てんかんの症状は、身体の一部がガクガクしてけいれんを起こすタイプもあれば、静かに意識を失うタイプなどさまざまです。
ここでは、典型的なてんかん発作についてご紹介します。
発作のおこる範囲による分類
発作の起こる範囲によって、部分発作と全般発作に分けられます。
部分発作は、脳の一部分が過剰に興奮することで、身体の一部分が勝手に動いたり、輝く点や光が見えたりするなどの症状が見られます。中でも、意識が保持されるものを「単純部分発作」、発作時に意識を失ってしまうものを「複雑部分発作」と呼んでいます。
全般発作は、脳全体が過剰興奮することで起こり、発作時は、最初から意識を失ってしまうケースがほとんどです。
症状の特徴からみた分類
症状の特徴からは大きく分けて以下の3つに分類されます。
| 種類 | 症状 |
|---|---|
| 強直間代発作 | ・手足を伸ばした状態で全身が固くなる ・手足をガクガクする発作が起こる |
| 欠神発作 | ・短時間、意識を失う症状に見舞われる。 ・話をするなど直前に行っていた動作が突然止まり意識を失う |
| ミオクロニー発作 | ・ビクンと筋肉が収縮する発作が起きる ・持っているものを投げ飛ばすほど強い発作が起きることもある |
子どもに多いてんかん発作

子どもによく見られるてんかんは以下の3つです。
| 種類 | 症状 |
|---|---|
| 中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん | ・寝入り際や寝起きに顔がピクピクしたりしびれたりする ・全身けいれんが起こることもある |
| 小児欠神てんかん | ・直前まで行っていた行動を突然中断し、動かなくなる ・数秒~数十秒ほどで突然終わり、またもとの行動を再開する |
| 若年ミオクロニーてんかん | ・朝起きた時にミオクロニー発作がおきたり、全身のけいれんが起きたりする |
子どもによく見られるてんかん発作には、大人になるにつれて治るてんかんもあれば、完全に治るのが難しいとされるてんかんもあります。
中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかんは、一般的に成人する前に治ります。小児欠神てんかんは、成人までに治る場合がほとんどです。ミオクロニーてんかんは、薬による治療を続けることで発作をおさえられます。
てんかんと併存しやすい発達障害
てんかんは以下の障害と併存しやすいと言われています。
注意欠陥多動性症(ADHD)
限局性学習障害(SLD)
子どものてんかんにおける発達障害の併存率は、てんかんでない子どもよりも高いです。
自閉スペクトラムで20%、注意欠陥多動性症で30%と言われています。そのうちの3分の2がてんかん発症後に発達障害の診断を受けています。
また、発達障害ではてんかんの併存率が高いです。自閉症スペクトラムでは、5~38%がてんかんを併せ持っています。特に知的障害を伴う場合は、知的障害を伴わない場合の約3倍ものてんかんの併存が確認されています。
てんかん発作が起きたときの対応

てんかん発作が起きたときには、慌てずに以下の行動をとりましょう。
- 安全な場所を確保する
- 呼吸しやすいように衣服をゆるめる
- 窒息を防ぐために横向きに寝かせる
- 発作時の状況を観察し記録をとる
一つずつ解説していきます。
安全な場所を確保する
まずは、発作を起こした子どもの安全を確保する必要があります。
階段や通路など危険を伴う場所で起きた場合には、安全な場所に移動させます。椅子に座っている場合には、椅子から降ろしましょう。
てんかん発作により体が動いた際、ケガをしないように周囲にあるものを取り除きます。眼鏡やベルトもケガをする恐れがありますので外しておくと安全です。
呼吸しやすいように衣服をゆるめる
襟元などの衣服をゆるめてあげると呼吸がしやすくなります。
発作が起きたときに、無理に口の中に指やタオルなどを差し込むのは危険です。無理に差し込むと歯が折れてしまったり、指をかまれたりしてしまいます。舌をかまないように支援したいときには、下あごを下から軽く上げてあげると効果的です。
窒息を防ぐために横向きに寝かせる
上を向いたまま寝ていると、嘔吐があった時に気道を詰まらせてしまう危険があります。体を横向きにして気道を確保するようにしましょう。
発作時の状況を観察し記録をとる
発作時は強く揺さぶったり、大きな声で声かけをしたりするのは逆効果です。優しく声をかけながら危険がないように見守ります。
時計があれば時間を計りながら、発作の様子を観察します。いつ、どこで、どのような症状がどれくらい継続したかなどを記録しておくと、発作の起こりやすい時間や誘発される要因などの把握が可能です。
てんかんの子どもが生活するうえで気をつけたいこと
てんかんの子どもが生活するうえで気をつけたいことは以下の3つです。
- 生活リズムを整える
- 長時間にわたるテレビやゲームは避ける
- 学校や病院と連携する
生活リズムを整える
睡眠不足は、てんかん発作を誘発する要因になりやすいと言われています。テレビゲームなどに没頭し夜更かしをしてしまうと、発作が起きやすくなってしまうので注意が必要です。
睡眠時間は、8時間〜10時間くらいを目安に十分とるようにします。なるべく睡眠不足が続かないように、規則正しい生活を心がけて生活リズムを整えましょう。
長時間にわたるテレビやゲームは避ける
長時間にわたってテレビを視聴したり、ゲームをし続けたりしていると、発作が起きやすくなりがちです。チラチラ光る刺激によって誘発される光過敏性てんかんもあります。
特に、視覚による刺激により発作が起きた経験がある場合は、長時間にわたり画面を見ることを避けましょう。
学校や病院と連携する
てんかんのある子どもが安全に楽しく学校で過ごすためには、通っている学校や病院などの専門機関と連携するとスムーズです。
学校には、てんかんの症状やお薬、配慮してほしいことなどを伝えておきます。子どもが自分で薬を管理するのが難しい場合には、適宜、言葉かけや支援をお願いしておきましょう。
また、薬の服用や副作用、生活で気になることがある場合には、主治医に相談して不安を取り除くようにします。
過度に心配せずに上手に付き合おう
子どものてんかんは、継続的な治療を受け、薬の服用などを怠らなければ症状をおさえられます。学校生活や日常生活において大きく制限を受けるようなことはありません。
ただし、薬の飲み忘れや水泳など水中での活動を行う場合には十分注意しましょう。また、てんかんだけでなく、発達障害を併せ持つ場合には、子どもの特性を理解し適切なサポートをする必要があります。
てんかん発作があるからといって行動に制約をかけてしまうと、子どもは経験不足から自分に自信がもてなくなってしまう場合もあります。過度に心配せずに、学校や病院と連携をはかりながら、子どもの生活体験を豊かにしていきましょう。
【参考】てんかんinfo|ユーシービージャパン株式会社小児のてんかん|慶應義塾大学病院てんかんとは|神戸大学医学部付属病院 てんかんセンターてんかんと発達障害|国立精神・神経医療研究センター
執筆者プロフィール
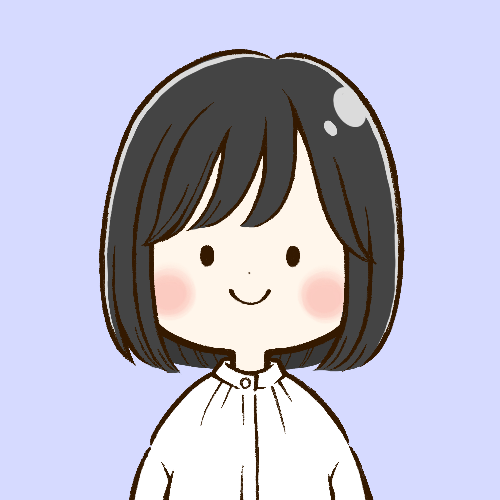
特別支援学校や小学校の特別支援学級に教員として勤務。さまざまな障害のある子どもとの関わりを経て、現在は、ライターとして福祉・教育を中心に執筆している。教員免許の他、保育士、社会福祉主事、手話検定2級の資格を保有。







