
企業における障害者雇用は、法定雇用率の達成という形式的な取り組みから、多様な人材の活躍による企業価値の向上へと、その意義が大きく変化しています。
本記事では、異なる業界で独自の取り組みを展開する4社の事例を通じて、障害者雇用における成功のポイントと、そこから見えてくる未来の可能性を探っていきます。
航空業界:ANAグループの取り組み

ANAグループは、障害の有無に関わらず全ての社員が生き生きと働ける環境づくりを目指しています。ANAグループは、障害者雇用を単なる法的義務としてではなく、社会的責任かつ重要な人材確保の機会として捉えています。
推進体制と実績
2012年にANA人事部内に「グループ障害者雇用推進室」を設置し、グループ全体での取り組みを推進しています。採用情報の発信、合同面接会の実施、教育展開などを通じて、積極的な雇用促進を行っています。
2024年6月1日時点での実績として、グループ40社合算の雇用率は2.71%に達し、38社が法定雇用数を達成しました。この数字は日本企業の平均雇用率を上回っており、継続的な向上を示しています。
行動規範「3万6千人のスタート」
2015年に策定された行動規範では、以下の点を重視しています。
障害に起因する働く上での不便さの解消
相互理解と個の尊重
可能性の追求と活躍機会の提供
この行動規範は、グループ各社の人事担当者と障害のある社員、合計50名以上による議論を経て策定されました。ANAグループは、この行動規範をベースに全社員が障害者雇用について正しく理解し、グループの総合力を高めることを目指しています。
具体的な職場での取り組み
ANAグループでの具体的な取り組みをご紹介します。
職場環境の整備
ANAグループでは、全社的にUDトークを導入し、聴覚障害者とのコミュニケーションをスムーズにする環境を整えています。2023年1月からは電話リレーサービスを開始し、聴覚や発話に障害のある社員の業務支援を強化しました。
また、2023年12月には合理的配慮ツールの購入、提供、管理を一元化することで、障害のある社員へのサポート体制を充実させています。
活躍事例
ANAウィングフェローズ・ヴイ王子での取り組みでは、障害のある社員が管理職を含むさまざまな役割で活躍しています。また、「ANA WOnderful Day」カフェの運営など、独自の取り組みも展開しています。
教育・啓発活動
ANAグループでは、定期的に障害者雇用推進者連絡会を開催し、グループ内での情報共有と方向性の確認を行っています。また、年に一度の啓発セミナーを実施し、外部講師を招いて理解促進を図っています。
さらに、オンデマンド学習教材を提供しており、すでに5千名以上の社員が受講を完了しました。採用面では、定期的に合同面接会を開催しており、2023年度にはグループ15社が参加し、100名以上のエントリーがありました。
ANAグループは、これらの総合的な取り組みを通じて、多様性を重視した職場環境の実現と、すべての社員が活躍できる企業グループを目指しています。
保険業界:東京海上日動火災保険の支援体制

障害のある社員が能力を最大限に発揮できる職場環境の実現は、企業の重要な社会的責任の一つです。東京海上日動では、障害のある社員一人ひとりに寄り添った支援体制を構築し、全社を挙げて共生社会の実現に取り組んでいます。
現状と基本方針
東京海上日動では、現在約300名の障害のある社員が営業・損害サービス部門など、全国のさまざまな職場で活躍しています。東京海上日動は、障害の有無に関わらず個人の持つ能力の多様性を重視し「互いを認め合い、互いに支え合い、互いに高め合う」という理念のもと、すべての社員が能力を最大限に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。
具体的な支援体制
具体的にどのような支援体制をとっているのかご紹介します。
職業生活相談員の配置
すべての障害のある社員に対して職業生活相談員を配置し、きめ細やかなフォロー体制を整えています。年に1回以上の定期面談を義務付け、以下の項目について重点的に確認しています。
手引きの整備と活用
長期的な就労支援のため、上司や同僚向けの手引きを作成しています。この手引きにはビルや設備のバリアフリー情報、障害の状況・部位に応じた具体的な配慮事項が書かれているのが特徴です。
そして、これまでに蓄積されたノウハウや実践的な対応方法が含まれており、職場での円滑なコミュニケーションを支援しています。
全社的な取り組み
社内Web上に障害についての理解と配慮に関する情報を掲載し、社員全体のノーマライゼーションの意識向上に努めています。社内での活用だけでなく、お客様への対応にも活かされています。
目指す姿
東京海上日動は、障害のある社員と共に働き、お互いが切磋琢磨しながら成長できる環境づくりを重視しています。ハード面とソフト面の両面からサポート体制を整え、すべての社員が自身の能力を最大限に発揮し、長く活躍できる職場の実現を目指しています。
情報サービス業界:奥進システムの環境づくり

奥進システムは、WEBアプリケーション開発を専業とする大阪市の企業です。従業員7名のうち5名が障害者であり、そのうち3名が在宅勤務を行っています。「インターネット技術を活用し、社会に対し貢献できる企業を目指す」という行動指針のもと、就労場所にとらわれない働き方を実現しています。
在宅勤務者の活躍
奥進システムで働く、頸椎損傷による1級の障害者2名は、正社員としてWebシステム開発の中核を担っています。1名はメインプログラマーとして顧客管理システムやショッピングサイトの開発に従事し、営業SEも担当しています。もう1名、システム開発の他、社内のIT環境の運用管理や技術動向の調査・研究が担当です。
働きやすい環境づくり
週5日勤務のうち、2日を在宅勤務(9:00〜18:00)、3日を通勤勤務(8:30〜17:30)として、体調管理と業務の両立を図っています。
コミュニケーション面では、Skypeを活用した朝礼の実施や日報による情報共有を行い、忘年会や会社行事にも参加しています。また、技術面では、VPN、リモートディスクトップなどの環境を整備し、自宅でも効率的に業務が行える体制を構築しているのが特徴です。
経営者と従業員の声
経営者は「彼らは社会とつながっていたいという想いが強く、仕事に対する姿勢がとても熱心です。特別な配慮は必要最小限で、今や職場になくてはならない存在です」と語っています。
在宅勤務者からは「体調管理に配慮した柔軟な勤務が可能で、やりがいのある仕事に携われる環境です。小回りが利き、風通しの良い会社で働きやすい」という声が寄せられています。
奥進システムの取り組みは、障害者雇用における在宅勤務の可能性を示す好事例です。
製造業:キョウセイの工夫

キョウセイは、1982年に社会福祉法人ひまわりの会後援会の有志によって設立された、障害者の社会自立を目的とした製造業企業です。倉敷化工株式会社から設備の貸与と技術指導を受け、産業用防振ゴム製品の製造を行っています。全従業員78名のうち54名が障害者であり、その大半が知的障害者です。
特徴的な事業運営
キョウセイでは、製造ラインの主工程をすべて障害者が担当しています。個々の能力や個性に合わせて適切な配置を行い、障害者同士で指導や補助を行う体制を構築しています。障害の程度で仕事を分けていません。個人の得意分野に着目した職場配置により、重度知的障害者でも高度な作業を担当することを実現しています。
就労支援の取り組み
障害者が安定して働き続けるためには、職場環境の整備だけでなく、生活面も含めた包括的なサポートが重要です。キョウセイでは、関係機関との連携、社員の成長機会の創出、作業環境の改善という3つの柱を軸に、きめ細やかな支援を展開しています。
総合的な支援体制
事業所(キョウセイ)、発注企業(倉敷化工)、生活支援機関(社会福祉法人ひまわりの会)が緊密に連携し、就労と生活の両面から安定した環境を提供しています。
成長を促す工夫
社員の適性を見極め、適切な作業配置を行うことで、自信とプライドを持って仕事に取り組める環境を作っています。習熟度が上がった社員は指導的立場へステップアップし、新入社員や実習生の教育も担当しています。
作業環境の改善
倉敷化工と共同で継続的な改善活動を行い、障害者が安全かつ効率的に働ける環境づくりに取り組んでいます。例えば、色による重量判別や、作業を簡略化する器具の開発など、さまざまな工夫を実践しています。
今後の課題と展望
創業から約30年が経過し、社員の高齢化への対応が課題となっています。作業内容の見直しや道具の改善により、年齢に関係なく働ける環境づくりを目指しています。また、地域への情報発信を強化し、障害者の就労可能性を広く示していく方針です。
キョウセイは「共に育ち、共に生きる」という理念のもと、障害者の社会自立と、すべての社員が生き生きと働ける職場づくりを続けています。
株式会社キョウセイ
まとめ
紹介した4社の事例から、成功する障害者雇用には以下の共通点があることがわかります。
一つは、障害者雇用を単なる法的義務としてではなく、企業の成長機会として捉える経営姿勢です。ANAグループの行動規範策定や、キョウセイの事業運営方針に、その考えが明確に表れています。
次にきめ細やかな支援体制の構築です。東京海上日動の職業生活相談員制度や、奥進システムの柔軟な勤務体制など、各社が独自の工夫を重ねています。
最後は障害の特性に応じた職場環境の整備です。業務内容の最適化や必要な設備の導入など、各社が継続的な改善に取り組んでいます。
これらの事例は、障害者雇用が企業の成長と共生社会の実現の両立に寄与することを示しすものです。今後も、テクノロジーの進化や働き方改革の推進により、さらなる可能性が広がることが期待されます。
執筆者プロフィール
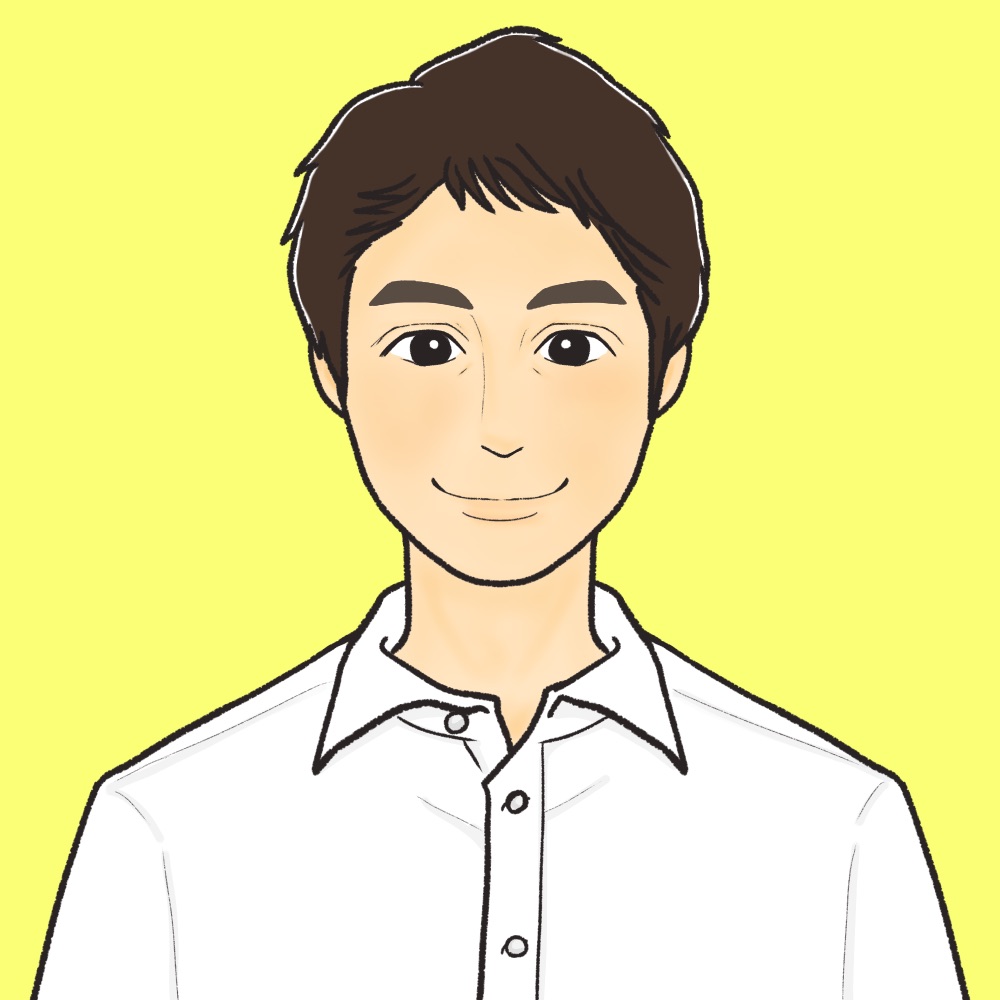
「情報は人を助ける力になる」をモットーに執筆活動を行うライター。
社会経験を活かし、消費者保護や労働法規の分野で独自調査を重ねている。得意分野は法制度や行政手続きのほか、キャリア形成論、ビジネススキル開発など。







