 「フリースクールってどんなところ?」「通うのに費用はかかるの?」「実際のところ通うメリットはある?」と、疑問を持っている方も多いかもしれません。
「フリースクールってどんなところ?」「通うのに費用はかかるの?」「実際のところ通うメリットはある?」と、疑問を持っている方も多いかもしれません。
フリースクールとは、不登校や引きこもり、発達障害をもつ子どもを対象に学習や生活のサポートをしてくれる民間施設です。フリースクールの規模や活動内容は多種多様であるため、自分に合ったスクールを選ぶ必要があります。
この記事では、フリースクールの種類や費用、通うメリット・デメリットについて解説しています。フリースクールについて知りたい方は、参考にしてみてください。
フリースクールとは?
フリースクールとは、何らかの事由により学校に通えない子どもを対象に学習や生活をサポートする民間施設です。例えば、不登校や引きこもり、発達障害をもつ子どもに対して学習や体験学習の場を提供したり、教育相談、心のケアなどにも対応してくれたりします。
運営の主体は、NPO法人やボランティア団体、個人経営などの民間施設です。民間の自主性や主体性に基づいて運営されており、その規模や活動内容は多種多様です。
フリースクールには入学条件がなく基本的に誰でも通えます。不登校の小中学生だけでなく、高校生も利用できます。
フリースクールの種類6つ

フリースクールは以下の6つの種類があります。
- 子どもの居場所を提供するタイプ
- 学校復帰を目指し学習をサポートするタイプ
- 専門家や医療機関と連携しているタイプ
- 独自の教育方針を掲げているタイプ
- 自宅訪問やオンラインでサポートするタイプ
- 共同生活をするタイプ
それぞれ見ていきましょう。
子どもの居場所を提供するタイプ
学校に通えなくなる子どもの中には、学校や家庭での悩みやストレスを抱えて気持ちがダウンしている場合もあります。その場合は、自信や元気を取り戻すために安心して過ごせる環境が必要です。
子どもの居場所を提供するタイプのフリースクールでは、信頼できるスタッフや子どもたちと交流を持ちつつ自分のペースで過ごせます。安心できる環境で自由に過ごすことで、子どもの心の傷の回復を促し自信を取り戻すことを重視しています。
学校復帰を目指し学習をサポートするタイプ
スムーズに学校に復帰できるように、学習面のサポートに力を入れているのが特徴です。
学習の遅れがある場合には学習状況に応じたサポートを行ってくれます。中には専科の先生が教えてくれたり、進路先の相談にも応じてくれたりするフリースクールもあります。
学校の進度に合わせた学習サポートを行ってくれるため、学校に行っていない期間の遅れも取り戻せるでしょう。
専門家や医療機関と連携しているタイプ
発達障害や学習障害を抱えている子どもは、学習や友人関係が上手くいかずに不登校になってしまう場合も少なくありません。
心理や教育の専門家と連携しているフリースクールでは、障害の特性に応じた学習支援や社会生活に適応するためのトレーニングが受けられます。また、医療機関と連携している場合には、医療的なケアが受けられます。
専門家や医療機関から適切なサポートが受けられるため、心の病や障害のある子どもも安心して通えます。
独自の教育方針を掲げているタイプ
独自の教育方針を掲げているフリースクールには、さまざまなタイプがあります。例えば、パソコンスキルや芸術、スポーツなど特定のスキルが学べるスクールや自然活動を行うスクールなどがあります。
学習以外にも一緒に何かを成し遂げていく中でやる気を育てることを目的にしています。
自宅訪問やオンラインでサポートするタイプ
学校に通えない子どもの中には、外出自体も難しかったり、新しい環境になじむ気力が持てなかったりする場合もあります。フリースクールに通うのも難しい場合には、スタッフが自宅訪問してくれるところを利用するのも1つの方法です。
自宅でスタッフと信頼関係を築きながら、少しずつ外に出る意欲や誰かと関わりたいという気持ちを育てていけます。近年では、自宅へ訪問せずに、オンラインでやりとりするフリースクールも増えてきています。
共同生活をするタイプ
複数の子どもと共同生活を送りながら、生活全体をサポートしてくれます。
共同生活を送るタイプのフリースクールには、規則正しい生活を送ることに重きをおいている場合もあれば、個々の意思を尊重することに重きをおいている場合もあります。
フリースクールとサポート校の違い
フリースクールとサポート校の違いは以下の通りです。
|
フリースクール |
サポート校 |
|
| 対象 | 基本的に誰でも通える | 通信制高校に通う生徒 |
| 目的 | 学校に通えない生徒の学習や生活のサポート | 通信制高校に通う生徒の学習サポート |
| 費用 | 月々の授業料 | 通信制高校の学費
サポート校の学費 |
フリースクールは、あくまでも民間機関であり、通い続けても高校の卒業資格の取得はできません。一方、サポート校の生徒は、通信制高校に在籍しているため、所定の単位を修めれば高校の卒業資格を得られます。
フリースクールと適応指導教室の違い
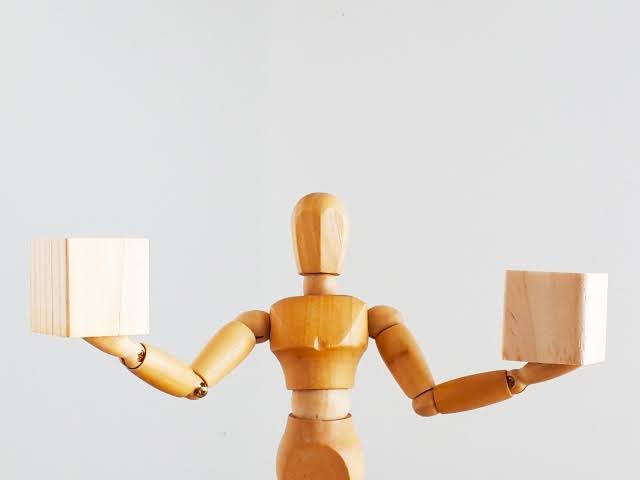
フリースクールと適応指導教室の違いは以下の通りです。
|
フリースクール |
適応指導教室 |
|
| 運営主体 | NPO法人など民間機関 | 教育委員会といった公的機関 |
| 目的 | 学校に通えない子どもの学習や生活のサポート | 在籍していた学校に通えるようになるためのサポート |
| 出席扱いの可否 | 出席扱いにならない場合もある | 出席扱いになる |
| 費用 | 入学金や授業料がかかる | 無料 |
フリースクールは、入学条件がなくすぐに通えます。一方、適応指導教室に通う場合には、手続きに時間を要し、通えるようになるまでに3か月程度かかる場合があります。
フリースクールにかかる費用

フリースクールに通うには費用がかかります。入学金と月々の会費(授業料)を払うのが一般的です。
義務教育段階の小中学生が通うフリースクールの入学金の平均は、約5万3,000円で、約3割が1万円~3万円の間となっています。
また、月々の会費(授業料)は、約3万3,000円です。「1万円〜3万円」「3万円〜5万円」としているフリースクールが約4割となっています。
フリースクールに通うメリット
フリースクールに通う主なメリットは以下の3つです。
- 自分のペースで通える
- 社会とのつながりができる
- 専門家のサポートが受けられる
それぞれ解説していきます。
自分のペースで通える
フリースペースでは、学校のように決まった日課があるわけではなく、自分のペースで自由に過ごせます。 学習も自分のレベルに合った学習ペースで進められます。
また、自分の好きな活動を選べるため、得意分野を伸ばしていくことも可能です。
決められたスケジュールに沿って行動するのが苦手だったり、自分の興味関心がない分野には集中できなかったりする子どもにとっては、過ごしやすい環境といえるでしょう。
社会とのつながりができる
学校に通えなくなると家庭にしか居場所がなくなり、社会とのつながりが薄くなってしまいます。 社会との接点がなくなってしまうと精神的に不安定になる場合もあるでしょう。
フリースクールには、同じような境遇や悩みを抱えている子どももたくさんいます。同じような悩みを持つ子どもと交流を持つことで、自分自身を肯定し安心感を得られます。
専門家のサポートが受けられる
フリースクールでは、カウンセラーに相談しやすい環境が整っています。親や友人には相談しにくいことも、カウンセラーや専門家に親身に聞いてもらえると心が軽くなるでしょう。
また、発達障害などがあり学習や生活に困難を感じている場合には、専門家による障害の特性に応じたサポートが受けられます。
フリースクールに通うデメリット
フリースクールに通うデメリットは以下の2つです。
- 費用がかかる
- 学校への出席日数にならない場合がある
それぞれ見ていきましょう。
費用がかかる
公立の小中学校の授業料はほぼ無償ですが、フリースクールは入学金や月々の授業料などの費用がかかります。また、自治体で助成金を出している場合もありますが、地域によってばらつきがあるため必ず受け取れるとは限りません。
フリースクールにかかる費用により少なからず経済的な負担が増えてしまうでしょう。
学校への出席扱いにならない場合もある
フリースクールに通った日数が必ずしも出席扱いになるとは限りません。在籍する学校長の判断により、出席扱いにならない場合もあります。
小中学校では、原則、出席日数に関わらず進級や卒業は認められます。しかし、出席日数が少ないと、高校進学時の内申点に影響を及ぼす可能性があります。フリースクールへの通学が出席扱いにならないと高校受験で不利になってしまうかもしれません。
フリースクールは1つの選択肢
フリースクールは、学校に通えない状態にある子どもたちにとって、自分のペースで過ごせる安心できる場所です。子どもたちは、個別の支援や多様な活動を通して自信ややる気を取り戻せる可能性が高まるでしょう。
しかし、不登校の子どものサポートをしてくれる場所はフリースクールだけではありません。
フリースクールは1つの選択肢として捉え、子どもの意思や気持ちを尊重しながら、子どもに合った選択肢を選ぶようにするとよいでしょう。
【参考】何らかの理由で学校に通えない子どもを対象に学習や生活などの支援を行う民間の施設フリースクール|一般社団法人全国PTA連絡協議会 フリースクール・不登校に対する取組|文部科学省
執筆者プロフィール
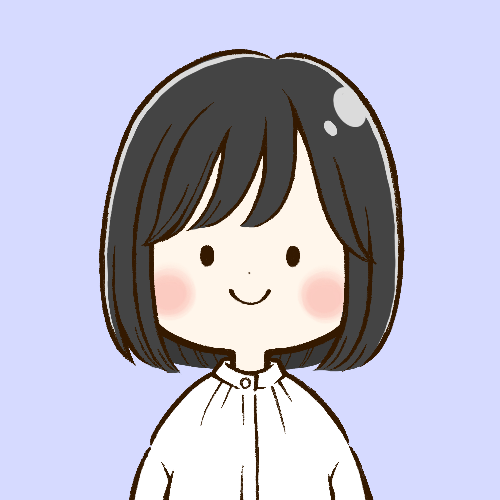
特別支援学校や小学校の特別支援学級に教員として勤務。さまざまな障害のある子どもとの関わりを経て、現在は、ライターとして福祉・教育を中心に執筆している。教員免許の他、保育士、社会福祉主事、手話検定2級の資格を保有。







