 「家では問題なく話せるのに、幼稚園や学校では全く話せない…」
「家では問題なく話せるのに、幼稚園や学校では全く話せない…」
「学校では、特定の先生や友達としか話せない…」
このような状態が長く続いている場合には、場面緘黙症の可能性があります。場面緘黙症は、家では普通に話せるのに、学校などの社会的環境では話せない状態が続く不安症の1つです。発達障害と併せ持つ子どもも多く見られます。この記事では、場面緘黙症の原因や症状についてわかりやすく解説しています。発達障害との関係や適切な支援方法についても解説していますので参考にしてください。
場面緘黙症とは?
場面緘黙症とは、家などのリラックスできる場所では普通に話せるのに、学校や幼稚園など、話すことを期待される社会的環境では話せない状態を指します。自分の意志で話さないわけではなく、本人は話したくても話せずに困り感を抱えています。
発症時期は、2歳〜5歳未満の幼少期が最も多いです。先生や友達との交流や発表の機会が増える入園・入学の時期に明確に症状が現れてきます。また、男児よりも女児に多く見られる傾向にあります。
以前は、「選択性場面緘黙」とも呼ばれていましたが、「自ら話さないことを選んでいる」との誤解を招きやすいため、現在では「場面緘黙」が一般的に広く使われるようになってきています。
場面緘黙症の原因
場面緘黙症の原因は、まだはっきりとは解明されていません。しかし、生まれつき不安になりやすい気質や話すことがストレスとなる環境など複数の要因が絡み合って発症するといわれています。
例えば、以下のような要因が複数絡み合っている場合が多いと考えられています。
- 生まれつき不安を感じやすい性質を持っている
- 自分が話しているのを人に見られたり、聞かれたりすることへの不安を強く感じる
- 幼稚園や小学校への入学、引っ越しなどの急激な環境の変化
- 言葉やコミュニケーションなどに発達上のつまずきや苦手がある
生まれつきの性質や急激な環境の変化が影響している場合が多く、親の育て方や家庭環境との因果関係は認められていません。
場面緘黙症の症状
場面緘黙症は、家などのリラックスした環境では話せるのに、学校や幼稚園など特定の社会的環境では話したくても話せない状態が1か月以上続きます。
ただし、症状は人によってさまざまです。家庭でも家族以外と話せない子どももいれば、学校や幼稚園以外の場所でも話せない子どももいます。小さな声でなら話せる場合もあります。
また、声を出して話せないだけでなく、「かん動」と言われる身体の動きが抑制されてしまうケースも見られます。
場面緘黙症の子どもが抱える困りごと
 場面緘黙症の子どもは「話したくない」と意図的に選んで話さないのではありません。話そうと思っても声が出なくなってしまい話せない状態が続きます。
場面緘黙症の子どもは「話したくない」と意図的に選んで話さないのではありません。話そうと思っても声が出なくなってしまい話せない状態が続きます。
そのため、以下のような困りごとを抱えてしまいがちです。
- あいさつや雑談ができない
- 友達となじめない
- わからないことを質問できない
- 授業で発表したり、教科書を音読したりできない
場面緘黙症の子どもは思うように話せないため、学業やクラスメイトとのコミュニケーションにおいて支障をきたしてしまいます。しかし、場面緘黙症は、まだ広く知られておらず、「人見知りが激しい子」「おとなしい子」など性格の問題と捉えられて適切な支援が受けられない場合も多いです。
適切な支援が受けられないと、不登校やうつ状態を引き起こしたり、大人になってからも症状に悩まされたりする場合もあります。
場面緘黙症と発達障害との関係
場面緘黙症は法律上は発達障害者支援法の対象です。学校教育では、情緒障害として特別支援教育の対象となっています。医学的には、不安症の1つとして分類されており、発達障害には含まれていません。
しかし、場面緘黙症の子どもの中には、発達障害の特性を持っているケースも少なくありません。海外の調査では、場面緘黙児の68.5%に発達障害との併存が見られたとの報告もあります。
場面緘黙症と併存しやすい発達障害は以下の通りです。
- 自閉症スペクトラム(ASD)
- 注意欠陥多動性症(ADHD)
- 学習障害(LD)
- 発達性協調運動障害(DCD)
場面緘黙症は、話したくても話せない症状により、併存している発達障害に気づかれにくい場合があるため注意が必要です。また、発達障害を持っている子どもに適切な支援がされていない場合、環境に適応できずにさまざまな症状が現れることがあります。その一つの症状として場面緘黙症の症状が出る場合があります。
発達障害が併存している場合には、その特性による困り感にも寄り添って支援することが非常に大切といえるでしょう。
場面緘黙症の診断基準
 場面緘黙症の診断基準は、国際的な診断マニュアルDSM-5-TR(精神疾患の診断基準書)に基づいています。
場面緘黙症の診断基準は、国際的な診断マニュアルDSM-5-TR(精神疾患の診断基準書)に基づいています。
場面緘黙症は、家庭では話せますが、話すことが期待されている特定の社会的環境(学校など)では、話したくても話せない状態が続いている状態です。その期間が1か月以上続き、症状が継続することで、学業や対人コミュニケーションが妨げられていることが挙げられます。
また、話すことができないのは、その社会的状況で要求される話し言葉の知識、または話すことに関する楽しさが不足していることによるものではないとされています。
さらに、話せないことの原因は、社会的コミュニケーション症(言語症や吃音など)、自閉症スペクトラムや統合失調症などの他の疾病や障害によるものではないことも基準の1つです。
場面緘黙症が疑われる場合には、精神科や心療内科を受診すると、診断基準や子どもの様子などを総合的に判断したうえで診断してくれるでしょう。
適切な支援方法
場面緘黙症の子どもを支援するときは、単に話せない状態に注目するのではなく、その背景にある不安に上手に対応できるスキルを身につけさせることが大切です。子どもが抱えている不安を軽減できるようにサポートしましょう。
本人に「話しなさい」とプレッシャーをかけたり、「どうして話せないの?」と詰問したりするのは避けましょう。本人もなぜ話せないのかわからずに困っています。子どもの不安な気持ちに寄り添い、肯定的な言葉かけをするようにします。
また、無理に人前で話をさせたりせずに、少しずつできることから始めていきます。本人にとって不安が少ない場面から徐々に話す機会を設けるなどスモールステップで進んでいきましょう。
また、場面緘黙症の子どもが安心できる環境を用意することが大切です。家庭と学校が連携して安心して過ごせる環境を整えましょう。場面緘黙症は、特別支援教育の対象となるため通級指導教室などを利用することも可能です。
心療内科や精神科を受診すると、必要に応じて不安を和らげる薬などを処方してくれる場合もあります。
専門家の指示を仰ぎながら、本人にとって必要なサポートを行うようにするとよいでしょう。
場面緘黙症には適切な支援が大切
場面緘黙症は、家などでは普通に話せるのに学校や幼稚園などの特定の場所では話そうとしても話せない状態が続く不安症の1つです。
医学的には不安症と位置づけられていますが、発達障害と併存している場合も多いです。発達障害を併せ持つ場合には、それぞれの障害の特性に応じた支援が必要です。
場面緘黙症の子どもは、不安や緊張から話したくても話せないため特有の困り感を抱えていますが、性格からくるものと捉えられがちです。適切な支援が受けられないと不登校やうつ状態などの二次障害を引き起こす可能性が高くなってしまいます。
場面緘黙症の場合には、適切な支援や治療を受ける必要があります。学校や医師などの専門家に相談しながら適切なサポートをしていきましょう。
【参考】
かんもくネット
日本場面緘黙研究会
場面緘黙児に関する研究の展開
執筆者プロフィール
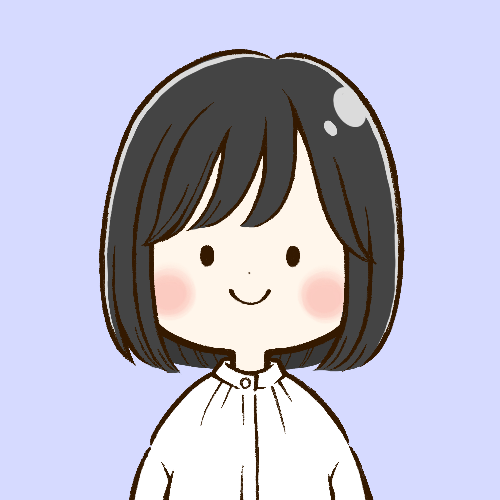
特別支援学校や小学校の特別支援学級に教員として勤務。さまざまな障害のある子どもとの関わりを経て、現在は、ライターとして福祉・教育を中心に執筆している。教員免許の他、保育士、社会福祉主事、手話検定2級の資格を保有。







