
「うちの子は発達障害なのかな?」
「発達障害を持つ小学生はどんな特徴があるの?」
「もし発達障害だったらどうすればいい?」
小学生になると学校での集団生活が始まります。友達との関係や学習でつまずきが目立つようになると、子どもの発達に問題があるのではないか?と不安になる方も多いかもしれません。
発達障害のある小学生は、周りとうまくコミュニケーションがとれないなどの特徴があります。その他にもさまざまな特徴があるため、本記事で解説していきます。
また、発達障害かもしれないと思ったときに相談できる支援機関や適切な対応方法についても解説しています。子どもの発達に不安を感じている方は、参考にしてください。
発達障害とは?
発達障害は、脳機能の発達に関係する障害です。
発達障害があると、コミュニケーションや学習に困難が見られます。そのため、周囲から「自分勝手」「変わった子ども」などと誤解されることも多いです。
原因は、生まれつきの脳の障害といわれており、決して親のしつけや本人の努力が足りないわけではありません。
発達障害の種類は主に3つ
小学生によくみられる発達障害には、以下のような種類があります。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠陥多動性症(ADHD)
- 学習障害(LD)
自閉スペクトラム症(ASD)は、コミュニケーションや社会性に困難がみられる障害です。
言葉の発達の遅れや興味の範囲がせまく、特定のものにこだわるなどの特徴がみられます。
このうち、知的な遅れをともなわない自閉症を高機能自閉症、言葉の遅れをともなわない自閉症をアスペルガー症候群と呼んでいます。
注意欠陥多動性症(ADHD)は、年齢や発達段階に不釣り合いな注意力や衝動性、多動性があり日常生活や学習に困難がみられる障害です。
学習障害(LD)は、全般的な知的発達の遅れはないにもかかわらず、聞く・話す・読む・書く・計算する・推論する能力のうち特定の能力に著しい困難がみられる障害です。
発達障害には種類がありますが、複数の障害をあわせ持つ場合も多いです。また、年齢や環境により目立つ症状が違ってくることもあるため、診断された時期によって診断名が変わる場合もあります。
発達障害がある小学生の特徴は?
発達障害があると、周りとうまくコミュニケーションがとれなかったり、学習についていけなくなったりしてしまいがちです。
特に、小学生になると集団行動が増え、友人関係なども複雑になるため、さまざまな場面でつまずきが目立つようになります。
発達障害がある小学生によく見られる特徴は、主に以下です。
| 人とのかかわり方 |
|
|---|---|
| コミュニケーション |
|
| 想像力 |
|
| 注意・集中 |
|
| 感覚 |
|
| 運動 |
|
| 学習 |
|
| 情緒・感情 |
|
小学生の子どもに発達障害があるかも…と感じた場合には
発達障害があると、対人関係や学習などさまざまな場面で問題に直面します。
失敗体験が多くなり、そのことを周りから責められてしまうと悩んでしまったり、やる気を失ったりしてしまいます。学校に行くこと自体がストレスとなり、不登校や引きこもりなどの二次障害を引き起こすことにもなりかねません。
適切な療育を受ければ苦手なことができるようになるなど、子どもが抱える困り感を改善できます。できることが増えると自己肯定感が育まれ心の安定にもつながるでしょう。
まずは、早期発見が大切です。少しでも発達に不安や違和感を感じた場合には、学校や以下の支援機関に相談してみましょう。
【相談できる支援機関】
児童相談所
保健所
発達障害者支援センター
発達障害がある小学生への適切な対応方法
発達障害は、障害の種類や程度によって特性はさまざまで、生活の中で困っていることは異なります。子どもの特性に応じたかかわりを工夫することが大切です。
発達障害がある子どもに対応する場合には、
- 説明はなるべく短い言葉で具体的に行う
- 視覚的にわかりやすく提示する
- 安心できる環境を整える
- 子どもの気持ちを受け止めてあげる
- できることを増やし、困ったときの対処法を一緒に考える
以上のポイントをおさえて接するとよいでしょう。
説明はなるべく短い言葉で具体的に行う
発達障害がある子どもにあいまいな言葉で指示を出しても伝わりにくいです。
言葉で説明するときは、具体的にどんなふうにしてほしいのかはっきり伝えます。
例えば、「ちゃんと持ってきて」ではなく、「お茶碗を台所まで持ってきてね」など具体的にしてほしいことを伝えましょう。
また、長い文章で説明するのもわかりにくいです。短文で1つ1つ順を追って説明するとよいでしょう。
視覚的にわかりやすく提示する
発達障害がある子どもは言葉で聞くよりも、目で見るほうがわかりやすい傾向にあります。特に自閉スペクトラム症の子どもには有効です。
スケジュールや手順などを視覚的にわかりやすく提示すると見通しがもて安心して過ごせます。
安心できる環境を整える
発達障害があると音や光など苦手な刺激を持っている場合が多いです。苦手な刺激があると落ち着かなくなり不安な気持ちを増長させてしまいます。
苦手な刺激をできるだけ排除し、安心して過ごせるような環境を用意しましょう。
子どもの気持ちを受け止めてあげる
初めてのことで見通しが持てないなど、不安から気持ちが高ぶり自分でコントロールできなくなってしまうときがあります。
そんなとき、やめさせようと強く叱りつけても余計にパニックになってしまいます。
子どもの気持ちを受け止め、クールダウンする時間をとるようにしましょう。
できることを増やし、困ったときの対処法を一緒に考える
発達障害がある子どもは、苦手なことが多く失敗体験ばかりしてしまいがちです。そのため自己肯定感が低い傾向にあります。
スモールステップでできることを増やすと、成功体験が増え自己肯定感も育まれます。
また、子どもが困ってしまったときは、どうやったらできるか子どもと一緒に考え安心感を与えるようにしましょう。
小学生の発達障害は早期発見が大切
小学生になると学校での集団生活が始まるため、発達障害があるとコミュニケーションや学習においてつまずきが目立つようになるでしょう。
頑張っているのにうまくいかない経験が続くと、子ども自身も辛くなってしまい不登校などの二次障害を引き起こしてしまう可能性もあります。
発達障害があっても適切な療育を受ければ、できることが増え自己肯定感を育めます。
もし発達に不安を感じている場合には、学校や支援機関などに相談するとよいでしょう。
【参考】
発達障害って、なんだろう|厚生労働省
発達障害とは|発達障害教育推進センター
発達障害の特性(代表例)|厚生労働省
発達障害のある子どもへの配慮|国立特別支援教育総合研究所
執筆者プロフィール
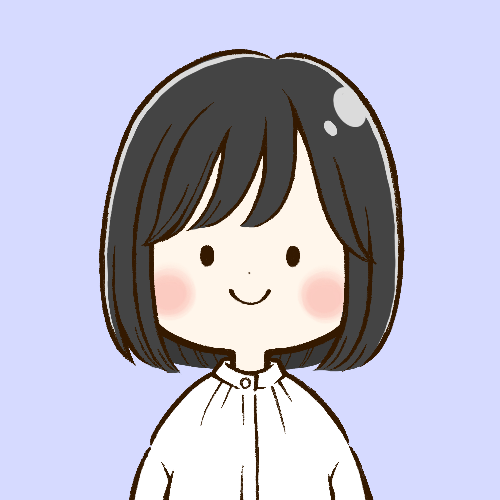
特別支援学校や小学校の特別支援学級に教員として勤務。さまざまな障害のある子どもとの関わりを経て、現在は、ライターとして福祉・教育を中心に執筆している。教員免許の他、保育士、社会福祉主事、手話検定2級の資格を保有。







