 「グレーゾーンで療育が必要と言われたけど本当なの?」
「グレーゾーンで療育が必要と言われたけど本当なの?」
「様子をみましょうと言われたけれど、発達に遅れが出ないか心配…」
など、子どもがグレーゾーンと診断され不安を抱えている保護者も多いでしょう。
グレーゾーンとは、発達障害の特性が見られるものの、医師が判断基準を満たしていると診断を下せない状態にあることを指します。発達障害の診断を受けている子どもに比べて、一見普通の子どもに見えるなど問題行動が目立たないケースも多いです。
この記事では、グレーゾーンの子どもが療育を受けるメリットや適切な支援方法、相談に応じてくれる相談機関について解説します。
発達障害のグレーゾーンとは?
グレーゾーンの子どもとは、保育や教育の場で不適応行動が見られるものの、診断がつかないあるいは未受診の子どものことです。
おもな発達障害には以下のような種類があります。
- 自閉スペクトラム症
- ADHD(注意欠陥多動性症)
- 学習障害
自閉スペクトラム症は、コミュニケーションに困難が見られる生まれつきの脳の機能障害です。例えば、順番や物の位置にこだわる、友達とうまく遊べないなどの特徴が見られます。
注意欠陥多動性症(ADHD)は、発達水準に不相応な不注意・多動性・衝動性が見られる発達障害です。常に動き回っていたり、よく物を失くしたりするなどの特徴があります。
限局性学習障害(SLD)は、知的発達に遅れがないにもかかわらず、読む・書く・聞く・話す・計算する・推論する能力のうち、特定の能力についてなかなか習得できない状態におちいります。そのため、小学校に入学して本格的に学習が始まると、つまずきが目立つようになるケースが多いです。
グレーゾーンは、上記のような発達障害の特性を持ちながら、それが障害なのか個性の範囲なのか診断がつかず、非常に曖昧な領域にいる子どもたちを指します。
グレーゾーンの子どもは療育を受けたほうがいい?
 結論から言えば、発達障害の特性をもつグレーゾーンの子どもは療育を受けた方がよいと言えます。
結論から言えば、発達障害の特性をもつグレーゾーンの子どもは療育を受けた方がよいと言えます。
グレーゾーンの子どもは、診断が降りている子どもより問題行動が目立たない傾向があります。軽度であるため特性を指摘されても、「病院を受診するほどではない」「この子の個性の範疇なのでは?」と考えてしまいがちです。また、保護者は不安でも、周りからは「様子をみましょう」と言われるケースも多いかもしれません。
しかし、特性に対する配慮がされないまま育つと、健常児と同じように振る舞うために過剰に頑張らなければいけなくなるなど、本人に強い負担がかかってしまうこともあります。
療育は、発達の状態に応じて社会生活をスムーズに営めるようにするためのサポートです。
早期に療育を受けることで、本人の困り感を減らしできることが増えていきます。
グレーゾーンの子どもが療育を受けるメリット
グレーゾーンの子どもが療育を受ける具体的なメリットは以下の通りです。
- 子供の発達を促せる
- 二次障害を防げる
- 保護者の不安軽減につながる
ひとつずつ解説していきます。
子供の発達を促せる
早期に適切な療育を受けると、子どもの発達が促され、社会性やコミュニケーション能力の向上が期待できます。療育では子どもの特性に合ったさまざまな発達支援が行われます。
専門の資格を持った職員により、子どもの発達段階に応じて適切な支援を行うことで、子どもの発達が促されできることを増やしていけます。
二次障害を予防できる
グレーゾーンの子どもは、判定を受けている子どもに比べて障害が見えにくいです。周囲から理解が得にくく十分なサポートが受けられない場合も多く見られます。そのため、健常児と同じようにすることを求められ、うまくできずに失敗を繰り返して自信を失ってしまいます。
また、グレーゾーンの子どもは、落ち着きがなかったり、集団行動が苦手で皆と一緒に行動できないケースも多いです。そのような特性により、周囲から「なぜ皆と行動できないの?」「ちゃんとしなさい。」などと叱責を受け続けていると、次第に自己肯定感が低くなってしまいます。
このように自信を失い自己肯定感が低くなると、行きしぶりや不登校、最悪の場合は、うつ病など二次的な障害を引き起こすケースも少なくありません。
療育を受けると、周囲に特性を理解してもらえる環境で、特性に応じた問題の解決方法を学べるため、二次障害を防ぐことができるでしょう。
保護者の不安軽減につながる
子どもが療育を受けるようになると、適切なかかわり方で障害に向き合えるため、子どもの持つ特性が軽減される傾向にあります。
また、児童発達支援センターなど療育を受けられる機関では、専門の資格を持った職員が子育ての相談にのってくれます。また、同じような特性の子どもを持つ保護者とのつながりが生まれ情報交換の場にもなるでしょう。
保護者にとっても子育ての不安やストレスを解消できるメリットがあります。
グレーゾーンの子どもへの適切な支援方法
ここでは、グレーゾーンの子どもに家庭でもできる適切な支援方法を紹介します。家庭でも適切なかかわりを持つと子どもの成長につながります。
ぜひ参考にして子育てに取り入れてみてください。
子どもの特性を理解する
グレーゾーンの子どもにどんな特性があるのか把握して理解を深めましょう。グレーゾーンと言っても、自閉症スペクトラムの傾向がある子ども、ADHDの傾向がある子どもなど特性は人それぞれです。
まずは、子どもの興味・関心がどこにあるのか、得意なことや苦手なことは何か把握することから始めましょう。どんなところに発達の凸凹があるのか特性を理解し、その特性に応じた接し方をすると子どもも過ごしやすくなります。
日頃から子どもの行動をよく観察し、特性だと思われることや困りごとを具体的に記録しておくのもよいでしょう。ノートやメモアプリ、動画など自分が記録を残しやすいもので記録しておくと専門機関に相談するときにも伝わりやすいです。
具体的でわかりやすい伝え方をする
なるべく曖昧な表現をせずに具体的に伝えるとわかりやすいです。
例えば、「きちんと片付けなさい」ではなく「はさみは引き出しにしまってね」など具体的な言葉で伝えます。
また、一度にたくさんのことを伝えずに、ひとつずつ順を追って伝えます。言葉だけの指示では伝わりにくい場合には、絵や図、写真など視覚的な支援を用いるのも効果的です。
イラストでスケジュールを伝えたり、タイマーで時間を区切ったりすると、見通しがもてるため子どもは安心して過ごせます。
肯定的な言葉かけをする
子どもの行動を注意する場合には、「やめて!〇〇しないで!」など否定的な言葉をさけましょう。子どもにしてほしくない行動をとめるのではなく、してほしいことを「〇〇しようね」と言葉かけするようにします。
また、叱るときには頭ごなしに叱るのではなく、まずは子供の気持ちを受け止めて共感を示し諭すように話すと効果的です。
日頃からできたことに目を向けて、「よく頑張ったね」「〇〇もできるようになったね」などほめてあげると自己肯定感が育ちます。
子育てに不安を感じたら支援機関に相談しよう

グレーゾーンの子どもの特性は、健常児の子どもにも見られる特性が多く、線引きが難しい一面もあります。少しでも子どもの発達に不安を感じたら専門機関に相談してみるとよいでしょう。
保健センター
保健センターは、地域住民への保健サービスを提供してくれる公的機関です。乳幼児期からの発育を把握しているため相談しやすいでしょう。3歳児検診などで相談することもできます。
【参考】地域保健|厚生労働省
児童相談所
児童相談所は、子どもに関する幅広い相談に応じてくれます。子どもの発達に関する悩み相談にも対応可能で、必要に応じて他の専門機関も紹介してくれます。児童相談所では、発達検査を受けることも可能です。
【参考】児童相談所の概要|厚生労働省
児童発達支援センター
児童発達支援センターは、障害のある子どもを対象に、日常生活で必要な知識やスキルを身につけるためのトレーニングをうけられる通所型の施設です。療育手帳がなくても、医師の診断書などで障害があることが証明できれば利用できます。療育が受けられるだけでなく保護者の子育ての悩み相談にも応じてくれます。
【参考】児童発達支援センター|WAMNET
発達障害者支援センター
発達障害やその家族を支援してくれる支援機関です。発達障害の診断が確定していなくても利用できます。相談支援や発達支援、就職支援など幅広く対応してくれます。
【参考】発達障害者センターの事業内容|国立障害者リハビリテーションセンター
療育で子どもの発達をサポート
グレーゾーンの子どもとは、保育や教育の場で不適応行動が見られるものの、診断がつかないあるいは未受診の子どものことです。周囲から理解やサポートを受けられずに、失敗を繰り返して自己肯定感が低くなってしまう場合も見受けられます。
グレーゾーンの子どもが療育を受けるメリットは、療育によって心身の発達を促せることです。そのため、不登校やうつ病などの二次障害を防げたり、保護者の育児によるストレスの解消にもつながります。
もし、子どもの発達に不安を感じている場合には、支援機関に相談すると専門家のアドバイスやサポートが受けられます。一人で悩まずにお近くの支援機関に相談してみるとよいでしょう。
執筆者プロフィール
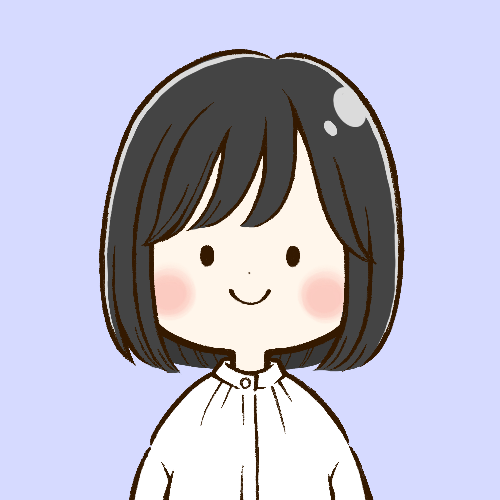
特別支援学校や小学校の特別支援学級に教員として勤務。さまざまな障害のある子どもとの関わりを経て、現在は、ライターとして福祉・教育を中心に執筆している。教員免許の他、保育士、社会福祉主事、手話検定2級の資格を保有。







